蕪村の自賛句(その一・一~十四)
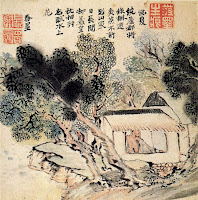
蕪村の自賛句(その一)
蕪村は生前に一冊の句集も出していない。蕪村没後、夜半亭二世・蕪村の後を継ぐ夜半亭三世・几董によて『蕪村句集』が刊行され、その巻末奥付けに「夜半翁発句集後編 近刻」との予告が書肆の手により掲げられていたが、几董自身によるそれは几董の逝去により実現することがなかった。これらの、蕪村自身の自選による「蕪村全集」の全貌の復元を試みようとしたものが、昭和四十九年に刊行された『蕪村自筆句帖』(尾形仂編著)である。それらの復元は、本間美術館蔵「蕪村自筆句稿貼交屏風」(略称、本間本)、諸家所蔵の蕪村自筆句帖断簡」(略称、断簡)、武田憲治郎氏旧蔵の「蕪村自筆句帖貼交屏風断簡」(略称、武田本)などを翻刻して進められた。
この復元された『蕪村自筆句帖』(尾形仂編著)の総句数は九百七十九句で、さらに、蕪村自身の手による「合点印」も復元されており、その合点印は几董の『点印論』も併せ紹介されていて、平点(一点)、珍重(一点半)、長点(二点)との区別であるという。そして、その句数は九十四句という。これらの九十四句は、蕪村の自選句のうちの蕪村自身による「自賛句・自信句」ともいえるものであろうと、尾形・前掲書には記載されている。これらの「自賛句・自信句」を尾形・前掲書によってその鑑賞を試みてみたい。
なお、句番号は、尾形・前掲書による。
三九 みの虫の古巣に沿ふて梅二輪
「本間本」所収。長点句とも珍重句とも取れる句。安永五年作。季語は、梅(春)。『蕪村全集(一)』の句意は、「蓑虫の古巣がぶら下がる同じ枝のすぐわきに、見れば梅花が二輪咲きそめた。春の到来を、昨秋来ぶら下がる蓑虫の古巣で強調する」。蓑虫は秋の季語だが、『蕪村全集(一)』では、この句の季語は梅の句として、尾形・前掲書でも「春の部」に収載されている。蓑虫は格好の俳材で、蕪村にも蓑虫の句は多い。芭蕉の句に「蓑虫の音を聞きに来よ草の庵」など。また、山口素道の「声おぼつかなまて、かつ無能なるを哀れぶ」(蓑虫説)などもある。蕪村にも、こうした格好の俳材の「みの虫」のその「古巣」と「咲きそめる梅二輪」とを対比して、その取り合わせで、この句を自賛句の一つにしているように思われる。
蕪村の自賛句(その二)
八八五 みの虫のぶらと世にふる時雨哉
「断簡」所収。「本間本」と「断簡」・「武田本」では「合点印」の相違があるが、尾形・前掲書によれば珍重句。ちなみに、前句(三九)は『蕪村全集(一)』では、珍重句の合点印が注意書きに記載されているが、尾形・前掲書では長点句の合点印のようにも思われる。
明和八年の作。季語は「時雨」。この句は兼題「時雨」(高徳院)の句。「世にふるもさらに時雨の宿りかな」(宗祇)、「世にふるもさらに宗祇の宿りかな」(芭蕉)の本句取りの句。現代俳句では類想句というのは極端に排斥する傾向にあるが、俳諧の発句においては、このような本句取りの句は盛んに用いられた技法の一つで、蕪村としても、兼題「時雨」での関連での本句取りの句として、この句を好句としていることは想像するに難くない。同年作の「六一九 みのむしの得たりかしこし初しぐれ」(本間本)には合点印はない。そして、この句も「初しぐれ猿も小蓑をほしげなり」の本句取りの句とも解せられる。これらのことからしても、いかに、蕪村が作句する時に芭蕉の句を常に意識していたかということも想像するに難くない。なお、掲出の句には、「ことば書(がき)有(あり)」との前書きがあるが、蕪村の小刷物に「感遇(偶)ことば書略す 夜行」との前書きのある「化そうな傘さす寺の時雨哉」との関連の注意書きが『蕪村全集(一)』に記載されている。『蕪村全集(一)』の句意は次の通り。「蓑虫は無為無能、細い糸にぶらりとぶら下がって疎懶に世を送り、降りかかる時雨にも平気な顔だ。無常観や風狂・漂泊の象徴とされてきた時雨の詩情に疎懶の楽しみを加えたもの。実はこの年、俳友大祇・鶴英を失った無常の思いの中で老懶の境地に居直った、蕪村自身の自画像」。この句意の「老懶の境地に居直った」というよりは、「老懶の境地の感偶」程度と解したい。なお、「世にふる」の「ふる」は「経る」と「降る」とが掛けられている。
蕪村の自賛句(その三)
八八七 古傘の婆娑(ばさ)と月夜の時雨哉
「断簡」所収。珍重句。季語は「時雨」(冬)。明和八年の作。この句は「古傘の婆娑としぐるゝ月夜哉」の句形で、安永六年に几董宛ての書簡に次のような記載が見られる。「月婆娑と申事は、冬夜の月光などの木々も荒蕪したる有さまニ用ひる候字也。秋の月に不用(もちひず)、冬の月ニ用ひ候字也と、南郭先生被申候キ(まうされさうらひき)。それ故遣ひ申事。ばさと云(いふ)響き、古傘に取合(とりあわせ)よろしき歟(か)と存(ぞんじ)候。何ニもせよ、人のせぬ所ニて候」。この書簡からして、掲出の句は安永六年の句形に改められているのかも知れない。『蕪村全集(一)』では、両方の句形(九六一・一九二〇)で収載している。いずれにしろ、明和八年から安永六年の六年の歳月を経ても、この句に執着していることからも、蕪村の自賛句の一つと蕪村自身が考えていたことは明らかなことであろう。そして、その自賛句の一つとした理由が、上記の几董宛ての書簡ではっきりと蕪村が指摘しているのである。即ち、「ばさと云(いふ)響き、古傘に取合(とりあわせ)よろしき歟(か)と存(ぞんじ)候。何ニもせよ、人のせぬ所ニて候」と、「取り合わせ」と「新味」との妙がこの句にはあるというのである。このことからこの句を蕪村は自賛句としているのであろう。『蕪村全集(一)』の掲出の句意は次の通り。「冬月が寒林を照らす荒涼の景に、突如として時雨が走ってきた。バサッと開いた古傘が月光に翻り、傘打つ音またバサッと鳴って、荒涼の感ここに極まる」。
蕪村の自賛句(その四)
八八三 音なせそたゝくは僧よふくと汁
「断簡」所収。珍重句。明和八年作。季語は「ふくと汁」(季語)。「ふくと汁」は「河豚汁」のこと。『蕪村全集(一)』・尾形・前掲書のいずれにおいも「ふぐと汁」と濁点は打たれていないが、濁点を付けて詠んでもさしつかえないものと解する。この河豚汁には、芭蕉の世によく知られた、「あら何ともなや昨日は過ぎて河豚汁」の句がある。この掲出の句も芭蕉のその句が背景にあろう。それだけではなく、中七の「たゝくは僧よ」は、「僧敲月下門」(賈島)の漢詩がその背景にあろう。『蕪村全集(一)』の句意は次の通り。「シイッ、物音を立てるな、門をたたいているのは、あのやかましい和尚だよきっと。せっかくの河豚汁の最中に殺生戒を振りかざされては、たまらんからな」。この句意にも見られる、この滑稽味の面白さを、蕪村は注目しているのであろう。蕪村の友人の三宅嘯山の『俳諧新選』にも収載されている句である。
(追記その一) 上記の三九「みの虫の古巣に沿ふて梅二輪」・八八七「古傘の婆娑(ばさ)と月夜の時雨哉」・八八三「音なせそたゝくは僧よふくと汁」は几董の『蕪村句集』に収載されている句で、このうち、「八八七・八八三」の句については、尾形・前掲書においては
句上に「珍重句」の印があり、句下に「平点印」があるが、この句下の「平点印」は『蕪村句集』に収載されている句の印であろうとされている(尾形・前掲書)。そして、「三九」
については、句下のこの「平点印」はなく、句上に付したもののようでもあり、そのことからすると、「三九」は「長点句」ではなく、『蕪村全集(一)』の注意書きにある「珍重句」と解すべきものと思われる。また、上記の八八五「みの虫のぶらと世にふる時雨哉」の句が句下に「平点印」がなく、即ち、几董の『蕪村全集』には収載されていないことは特記しておく必要があるように思われる。
(追記その二) 六五五「ふく汁の我活(い)キて居る寝覚(ねざめ)哉」・七二六「鰒汁の宿赤々と灯しけり」(本間本)は、几董の『蕪村全集』には収載されているが、句上・句下にもその収載の印の「平点印」はない。
蕪村の自賛句(その五)
六六七 ふく汁や五侯の家のもどり足
「本間本」所収。安永四年作。珍重句。季語は「ふく汁」(冬)。『蕪村全集(一)』の句意は次の通り。「ふぐ汁を馳走になっての帰り道。まるで五候の邸に招かれての珍味の饗宴にあずかったのごとく、腹も満ち足り酔歩まんさくとして定まらない」。そして、「五候 漢の成帝の時、同日に諸侯に封ぜられた皇太后王氏の一族五人をいう。五候、客の歓心を得んと競って珍膳を供した(西京雑記巻二)」との頭注が施されている。そして、この句は、蕪村没後に、蕪村の跡を継ぐ几董の『蕪村全集』には収録されていないで、河東碧梧桐の『蕪村十一部集』(昭和四年刊行)に収載されているところの『蕪村遺稿』に収録されている句なのである。即ち、几董が多分に蕪村自身が句集を編纂するとしたらとそれとなく準備をしていたと推測される、いわゆる、蕪村自選集ともいうべき『蕪村自筆句帖』を、蕪村没後に目にした時には、蕪村自身の自賛句の合点印の付いているこの句に、几董の目は留まらなかったということなのである。さらに付け加えるならば、几董は蕪村が自賛句としているこの句をそれほどのものとは考えていなかったとも思われるのである。そして、同時の頃の作とされている、「冬ごもり壁をこころの山に倚(よる)」などの句を、その『蕪村全集』に収録しているのである。掲出句とこの「冬ごもり」の二句を比較して、蕪村は「ふく汁」からの漢書の「五候」への連想ということを評価しているのに対して、几董は、「冬ごもり」の句の背景の「冬ごもりまた寄り添はんこの柱」(曠野)の芭蕉の句への連想などをより評価している、その差異のようにも思われるのである。そして、現在、これらの二句を比較して、蕪村の自賛句の掲出の句よりも、几董の『蕪村全集』に入っている蕪村自身の平点句の方が、より馴染み深いということを指摘しておきたいのである。そして、明治に入って「俳句革新」を成し遂げた正岡子規は、几董の『蕪村全集』の蕪村の句を高く評価して、この掲出の句の収載されている『蕪村遺稿』は知らずして亡くなってしまったのである。これらのことから、知らず知らずのうちに、几董や子規好みの蕪村の句を、現代人は多くの関心をもって、もう一面の、この「ふく汁と五候の取り合わせ」に「してやったり」と得意がっている蕪村のもう一面の姿というのを亡失しがちであるということは注意する必要があるということを特記しておきたいのである。
蕪村の自賛句(その六)
一 ほうらいの山まつりせむ老(おい)の春
「本間本所収」。安永四年(六十歳)作。平点句(『蕪村自筆句帖(筑摩書房刊))』 の解説の部には平点句の印がないが影印の部にはその合点印が読み取れ、『蕪村全集(一)』・『蕪村句集(岩波文庫)』でも合点句としている)。季語は「老の春」。几董の『蕪村句集』収録の、その冒頭の一句である。句意は「めでたく春を迎え歳(よわい)を一つ重ねたが、蓬莱飾りの蓬莱山を華やかにお祭りして、わが老いの春を祝いたい。人の生死を司る神として道家が祭る泰山府君の祭事に擬し、長寿の意をこめた」(『蕪村全集(一)』)。ここにおいても、「蓬莱」・「山まつり」と蕪村の南画の主題のようなものがこの句の眼目となっており、現代俳句という観点から鑑賞すると、やはり、蕪村の時代の南画家の元旦の句のような印象を受ける。ただ一つ、この句が蕪村の六十歳の還暦の元旦の句で、そういう観点から鑑賞すると、このときのこの句を作句している蕪村の姿が見えてくる。しかし、同年作の「海手より日は照(てり)つけて山ざくら」(合点印無し)の句の方が、現代人の好みであろう。しかし、こういう、何らの技巧が施されていない句については、蕪村自身は自賛句とは考えていないのである。やはり、これらの句に接すると江戸時代の蕪村との距離は大きいという感を深くするのである。
蕪村の自賛句(その七)
六 春をしむ人の榎(えのき)にかくれけり
「本間本」所収。明和六年(五十四歳)作。平点句。季語は「春をしむ」。この句は几董の『蕪村句集』には収載されていない。句意は「行く春を惜しんで郊行を楽しむ人の姿が、夏の木すなわち榎に隠れて見えなくなった。もう半分夏の世界の人となったらしい」(『蕪村全集(一)』)。この句意からも明瞭のように、蕪村がこの句を自賛句としているのは、「榎」が「夏」の「木」という「文字遊び」をしながら、「春」から「夏」へと移行する頃の「惜春」を主題にして、しかも、その榎に「人がかくれけり」と「おかしみ」の世界へ誘っているところにある。やはり、この句も単純な写生だけの句ではなく、当時の俳諧の、その豊穣な「笑い」の系譜に属するということに注目する必要があろう。
蕪村の自賛句(その八)
一九六 海手より日は照(てり)つけて山ざくら
「本間本」所収。安永四年(蕪村六十歳)の作。季語「山ざくら」。この句について、同年作の「一 ほうらいの山まつりせむ老(おい)の春」のところで「合点印」のない無点句として紹介したが、それは『蕪村全集(一)』(講談社)・『蕪村俳句集』(岩波文庫)のいずれにおいても、「合点印」が記載されていなかったということによる。ところが、『蕪村自筆句帖』(筑摩書房)の「影印」・「翻印」の両者においても「平点句」の表示がなされ、これはあきらかに『蕪村全集(一)』(講談社)・『蕪村俳句集』(岩波文庫)の記載漏れで、平点句と理解すべきである(それ故、「蕪村の自賛句その六」のその箇所はここで訂正)。
『蕪村全集(一)』の句意は次の通り。「海に面した山腹に山桜が満開だ。海上の朝日が光の束を投げ掛けるように、強烈に照らしている。海・山を一望にした大観の中で、山桜の最も美しいありようをとらえた」。この句意で十分であろうが、中村草田男は「蕪村は含蓄・余情・余韻などを一切考慮せず、青年のごとく単純に光の歓喜に酔っているいるのである。(中略)俳句は蕪村に至って初めて『青春』を持ったと言うことができる」(『蕪村集』)と指摘している。この草田男をして「俳句が初めて『青春』を持った」という、その「青春」に満ち溢れたこの句を、蕪村は晩年の六十歳のときに作句しているのである。そして、蕪村の絵画の絶頂期を迎える「謝寅」の号の時代はその三年後の、安政七年の頃からなのである。すなわち、いかに、蕪村が「画・俳二道」において晩成の人であったということが、この一事を取っても理解できるところであろう。この句に接すると、「馬酔木」の三羽烏の一人といわれた高屋窓秋の「ちるさくら海青ければ海へちる」が想起されてくる。蕪村のこの掲出の句は、蕪村自身の「平点句」ではあるが、蕪村の傑作句の一つとして、これからも詠み継がれていく一句と理解であろう。
蕪村の自賛句(その九)
一五六 三椀の雑煮かゆるや長者ぶり
「本間本」所収。『蕪村俳句集』(岩波文庫)では合点印のある句。平点句(「本間本」の写真版には合点印があるが、『蕪村自筆句帳』の解説文には合点印がない。『蕪村全集(一)』にも合点印の記載がない。転記漏れと思われる)。季語は「雑煮」(新年)。几董の『蕪村句集』にも採られている。安永元年(一七七二)、五十七歳のときの句。「貧しくとも、こうして達者な家族たちとともに新年を祝い、ちょっとした長者を気取って雑煮を三杯もお代わりすることよ。貧しいながら満ち足りた思い」が『蕪村全集(一)』の句意であるが、この「三椀」は「三杯もお代わりする」というよりも、「三重ねの椀で雑煮を食べる」という意味も込められていて、その「三椀」と「長者」との取り合わせの面白さに、蕪村はこの句に平点印を付したように思われる。蕪村の俳諧の師匠の早野巴人の句に「耕さず織らず雑煮の三笠山」というのがあり、この三笠山というのが「三重ね山」とを掛けていて、その巴人の句などが、この句の背景にあると理解したいのである。すなわち、この句も、蕪村の句の特質の、景気(叙景)・不用意(無作為)・高邁洒落(離俗)の、その洒落をより多く利かせている句と理解したいのである。
蕪村の自賛句(その十)
一二三 七(なな)くさやはかまの紐の片結び
「本間本」所収の句。平点句。但し、『蕪村自筆句帖』の写真版には平点印が付されているが、その解説文においては付されていない(記載洩れと思われる)。季語は「七くさ」(新年)。安永五年(一七七六)、六十一歳のときの句。几董の『蕪村句集』には「人日」(正月七日のこと)との前書きがあり、題詠の句と思われる。句意は「日ごろ袴など縁遠い年男が七草を打つのは儀式だからと袴姿でかしこまったものの、その紐は無造作な片結びになっている」(『蕪村全集(一)』)。この「人日」の句は蕪村の師の早野巴人などにも見られ、そして、内容的にも、その巴人や、巴人の師にあたる其角流の江戸座的な機智的な笑いを狙っての句作りで、現代俳人には決して好意的には見られない句でもあろう。そして、この江戸座の流れの俳人は「俳力」(俳諧本来の笑い)ということを重視しており、この句も
その範疇に入るものであろう。
蕪村の自賛句(その十一)
一○五 青柳や芹生(せりふ)の里の芹の中
「本間本」所収の句。平点句。安永六年(一七七七)、六十二歳のときの句。季語は「青柳」(春)。「芹」も春の季語だが、主たる季語の働きは「青柳」。「芹生の里」は洛北大原西方寂光院付近の古称で歌枕。西行の「大原は芹生を雪の道に開けてよもには人も通はざりけり」(山家集)を背景にしての一句。そして、地名の「芹生」と七草の一つの「芹」との言葉遊びも意識していることであろう。句意は「雪深く寂しい芹生の里にも、春ともなれば芹の群生する中に青柳が美しい翠色を見せている」(『蕪村全集(一)』)。この句もまた、この句の背景となっている西行の歌や芹生の地名と植物の芹との連想などの、いわゆる古典的な俳諧本来の手法を駆使してのもので、子規以降の俳人達は決して蕪村の代表句とは見なしてはいない。そして、蕪村やその俳諧の師の早野巴人などは、この掲出句に見られるように「季重なり」ということを厭わずに作句している例を多く見かける。
蕪村の自賛句(その十二)
四〇 鴈(かり)行(ゆき)て門田(かどた)も遠くおもはるゝ
一二七 鴈立(たち)て驚破(ソヨヤ)田にしの戸を閉(とづ)ル
「本間本」所収の句。この一二七の句については平点よりも上、長点よりも下の、「珍重の印」の珍重句。四〇の句は『蕪村自筆句帖』の写真版を見ては平点句のように思われる(『蕪村全集(その一)』)では珍重句の印が校注にある)。この二句とも几董編の『蕪村全集』に収載されている。四〇の句意は「今まで門前の田で餌をあさる雁の姿に親しんできたのに、春になって北へ飛び去ると、門田も寂しく心に遠い眺めになった」(『蕪村全集(その一)』)。一二七の句意は「田面の雁が北へ帰る。その羽音にビックリした田螺はスワ異変発生とばかり慌てて殻を閉じる」(『蕪村全集(その一)』)。この「驚破(ソヨヤ)」は白楽天の「驚破霓裳羽衣曲」(長恨歌)に由来があるという。それよりもなによりも、四〇の「帰雁」の句というよりも、この一二七の句は「田にし」の句なのである。そして、現代の俳句愛好者がこの二句を並列して鑑賞した場合、前者の「帰雁」の句の方を良しとする人の方が多いのではなかろうか。しかし、蕪村の時代においては、この滑稽句の一二七の「田にし」の句の方が歓迎されたのかも知れない。この二句とも安永五年(一七七六)の六十一歳の時の作である。この一二七の句に関連して、其角の句に、「鉦カンカン驚破郭公草の戸に」(五元集)があり、蕪村は、芭蕉・其角・巴人の江戸座の流れの俳人であったことを痛感すると共に、やはり、江戸時代の享保・安永時代の俳人であったことを痛感する。
蕪村の自賛句(その十三)
九八 夜桃林を出(いで)て暁嵯峨の桜人
「本間本」所収。珍重句。この句には「暁台伏水・嵯峨に遊べるに伴ひて」との前書きがある。この句も安永五年、蕪村六十一歳の時のものである。几董編の『蕪村全集』にも収載されている。そして、この句もまた現代俳句では余り歓迎されない「言葉遊び」的な技巧が隠されているのである。この「夜」は自分自身の号の「夜半亭」、そして、「暁」は尾張の俳人で蕪村一派と親交のあった、蕪村と並び称せられる中興俳壇の雄・加藤暁台のの号の「暁」を意味しているのである。しかも、「夜」と朝の「暁」をも意味していて、こういう句作りは、蕪村の俳諧の師の早野巴人も得意とするものであった。こういう技巧に技巧を凝らした挨拶句が、当時の俳人が競って作句したものなのであろう。句意は「昨日は遅くまで伏見の桃林に遊び、夜、桃林を出て、今日は早朝から嵯峨の桜花の下の人となっている」(『蕪村全集(一)』)と、どうにも、その句意を知って、こういう句を蕪村の数ある名句と称せられるものは度外視して、ことさらに自選句のうちの自賛句の印を伏している蕪村を思うと、今まで抱いて「郷愁の詩人・与謝蕪村」というようなイメージとかけ離れてくる印象は拭えないのである。
蕪村の自賛句(その十四)
五〇 花の香や嵯峨の燈火きゆる時
本間本所収。珍重句。安永六年、蕪村六十二歳のときの作。この句意は「夜桜見物の人も去って嵯峨の燈火が消えるころ、かすかな花の香が漂って来て、花の精に触れる思いがする」(『蕪村全集(一)』)。この句に出会ってやっと蕪村らしい句にひさびさにお目にかかったという思いである。これまで、蕪村が自分自身の手による自選句のうちで、さらに、長点・珍重・平点の、いわゆる点印を句頭に施したものは、技巧的な背後にその句に接する人に何かしらの謎解きを強いるような知的な作句姿勢というものが見て取れるものがほとんどであった。しかし、この句にはそういう他者に「句の巧みさや、人を驚かせるような作為的な操作」などを強いるものではなく、自分自身の「その時の感情や心の動き」を一句に託するという、作句するときの最もメインとするものを、この句に接する人に素直に語りかけてくるからに他ならない。この句については、蕪村自身愛着を持っていた一句のようで、「扇面自画賛」や几董宛の書簡なども残されている。そして、この句については、「華の香や夜半過行(すぎゆく)嵯峨の町」の別案の句もあり、相当に推敲を施した句であることも了知されるのである。
蕪村の自賛句(その二・十五~二十二)

蕪村の自賛句(その十五)
五二 水にちりて花なくなりぬ岸の梅
本間本所収。この句は最高点の印の長点句。安永六年(一七七七)、蕪村、六十二歳のときの作。「水にちりて花なくなりぬ崖の梅」(霞夫書簡)、「水に散ッて花なくなりぬ岸の梅」(『夜半叟句集』)との句形がある。この霞夫宛の書簡には、「此句、うち見ニはおもしろからぬ様ニ候。梅と云(いふ)ニ落花いたさぬはなく候。されども、樹下ニ落花のちり舗(しき)たる光景は、いまだ春色も過行かざる心地せられ候。恋々の情之有候。しかるに、此江頭の梅は、水ニ臨ミ、花が一片ちれば、其まゝ流水に奪(うばひ)て、流れ去り去りて、一片の落花も木の下ニハ見ぬ、扨も他の梅と替(かは)りて、あわ(は)れ成(なる)有さま、すごすごと江頭ニ立(たて)るたゝずまゐ(ひ)、とくと御尋思候へば、うまみ出候」との記載が見られる。蕪村がこの句を自分の句のうちで最高の作としているのは、「此江頭の梅は、水ニ臨ミ、花が一片ちれば、其まゝ流水に奪(うばひ)て、流れ去り去りて、一片の落花も木の下ニハ見ぬ」という、この着眼点がこの句の新味で、それに着眼したことに蕪村自身が満足の意を表しているのである。句意は「岸辺の梅は、地上に散り敷いて名残りを惜しませるよすがとてなく、水上に落ちるそばから流水に奪われたちまち流れ去ってしまう。後には老樹が寂しく残るばかり。『行くものはかくのごときか』と、花を伴って去った非常な時間を思う老蕪村の孤独な心境の表白」(『蕪村全集(一)』)。蕪村は、老成の画・俳二道を極めたものとして、この「行くものはかくのごときか」ということに大きな関心事があった。そして、一見して平凡なこの掲出句には、その老いていくものの老愁というものを託していることを、この「水にちりて」の上五から汲んで欲しいというのであろう。いかにも、蕪村らしい着眼点ではあるが、なかなかそこまで汲み取って鑑賞するのは至難の業のようにも思われる。
蕪村の自賛句(その十六)
六六 大門のおもき扉や春の暮
本間本所収。この句も最高点の印の長点句。天明元年(一七八一)、蕪村、六十六歳のときの作。「大門」の詠みは、『蕪村自筆句帖』では「だいもん」で、『蕪村全集(一)』では「おほもん」であるが、次の「おもき扉や」と呼応しての後者の詠みとしたい。この句は几董編の『蕪村句集』には収載されてはいない。句意は「春日もようやく暮れて、夕闇の中に寺の総門の大きな扉を閉ざすギィーッという鈍い音が吸い込まれてゆく。重さの感覚と春愁との調和」(『蕪村全集(一)』)。その句意の頭注に「春深遊寺客 花落閉門僧」(『詩人玉屑巻二〇』)に典拠があるとの関連記載が見られる。しかし、その漢詩文の典拠の背景は必須のものではなく、蕪村の絵画的な句の一つとして、そのイメージは鮮明に伝わってくる。蕪村がこの句を長点句としている理由は、その漢詩文の典拠に基づくものではなく、「大門のおもき扉」と「春の暮」との取り合わせの妙のように思われる。それは、「重さの感覚と春愁との調和」というよりも、「重さの聴覚的な音の世界から春愁の視覚的な映像の世界への誘い」というようなことを蕪村は感じとっているのではなかろうか。そう解することによって、この「大門のおもき扉や」の「中七や切り」の余情が活きてくるものと解したい。
蕪村の自賛句(その十七)
八五 祇(ぎ)や鑑(かん)や花に香炷(たか)ん草むしろ
本間本所収。この句も最高点の印の長点句。安永八年(一七七九)、蕪村、六十四歳のときの作。この句には「や鑑や髭に落花を捻りけり」という異形のものもある。は飯尾宗祇、鑑は山崎宗鑑で、共に、連歌・俳諧の始祖とも仰がれている人物である。「香炷かん」・「髭に落花」は、宗祇が髭に香を炷き込めた逸話(扶桑隠逸伝)に由来するものであろう。掲出の句意は「いにしえの先達、宗祇、宗鑑は香り高い風雅の足跡を残した。今の世の宗祇・宗鑑とも呼ぶべき諸子よ、私たちも花下に俳筵を繰り広げその遺薫を継ごう」(『蕪村全集(一)』)。いかにも高踏主義の文人好みの蕪村らしい句ではあるが、こういう句を、蕪村自身が、「これが私の俳諧(俳句)です」と後世に伝えようとして、自賛句の最高点の長点印を付けていることに、いささか戸惑いすら感じる。これが、当時の蕪村の一面の「晴れ」の世界であるとしたら、同年の作の「洟(はな)たれて独(ひとり)碁をうつ夜寒かな」の偽らざる「褻(け)」の日常諷詠の世界に、より多くの親近感を覚えるのである。そして、蕪村が密かに句集を編まんとして、そのうちの自信作と思っていた作品というのは、この掲出の句のような、特定の、そして、上辺だけの「晴れ」の世界のものが多いということも心すべきことなのかもしれない。
蕪村の自賛句(その十八)
一五二 飢鳥(うゑどり)の花踏みこぼす山ざくら
本間本所収。この句も最高点の印の長点句。安永三年(一七七四)、蕪村、五十九歳のときの作。この年には「なの花や月は東に日は西に」という夙に蕪村の句として世に知られている句がつくられているが、この有名な句には何らの点印も施されていない。しかし、几董編の『蕪村句集』には収載されており、そして、この掲出の花の句は『蕪村句集』には収載されていない。夜半亭二世・蕪村と夜半亭三世・几董とでは、やはり、それぞれの好みがあり、それらが反映された結果のことなのであろうか。掲出の句意は「人里離れた山桜の樹上に、餌に飢えた鳥が群がって荒々しく花を踏みこぼし、時ならぬ落花の景を現出している」(『蕪村全集(一)』)。この句の「飢鳥の」という蕪村の視線は鋭いし、全体的に画人・蕪村の句という雰囲気を有している。この年には「ゆく春やおもたき琵琶の抱心(だきごころ)」や、関東遊歴時代の思い出に連なる「ゆく春やむらさきさむる筑波山」
(結城の城址にこの句の句碑がある)など名句が多い。掲出の句もそれらの名句のうちの一つにあげられるものであろう。
蕪村の自賛句(その一九)
一六三 なのはなや魔爺(まや)を下れば日のくるゝ
本間本所収。最高点の長点句。安永二年(一七七三)、蕪村、五十八歳のときの作。この句は几董編の『蕪村句集』には収載されていない。この句は「菜の花や摩耶を下れば暮(くれ)かゝる」との句形のものもある。「摩耶」は六甲連邦の一つの摩耶山のこと。その山上に釈迦の母・摩耶夫人を祀る天上寺がある。句意は「摩耶山を参詣して山を下ってくると、春の日もようやく暮れかかり、摂津平野を埋めた一面の菜の花も、先刻までの明るい黄色から黄昏へと次第に変わってゆく」(『蕪村全集(一)』)。この句と同時の作に「菜の花や油乏しき小家がち」がある。この句の方が掲出の句よりも名の知られた句なのであるが、そこには何らの印も付されていない。この掲出句の眼目は、摩耶山と摂津平野を埋め尽くした
一面の菜の花との取り合わせの妙にあるのであろう。余り蕪村の佳句としては取り上げられていない句であるが、いかにも、摂津平野の淀川べりに生まれた蕪村の、その郷愁のようなものと、画人・蕪村の視点のようなものが感知される一句である。
蕪村の自賛句(その二〇)
一七〇 ゆくはるや同車の君のさゝめごと
本間本所収。最高点の長点句。安永九年(一八〇七)、蕪村、六十五歳のときの作。この句も几董編の『蕪村句集』には収載されていない。蕪村の王朝趣味の一句として名高い。「同車の君」は貴族の牛車に同乗する女性。「ささめごと」はひそひそ話のこと。句意は「晩春の都大路を、女性の同乗した牛車が静かに行く。牛車の中で身を寄せた佳人が、尽きることなき睦言をささやき続けている。暮春の情と車中のささめ言との照応」(『蕪村全集(一)』)。
蕪村俳諧の一面の特色として、実生活とはまったく関係のない古典趣味・貴族趣味・王朝趣味・空想的虚構趣味のものが顕著な句があげられる、この句もそうした類のものであろう。そして、こういう句は芭蕉などには見ることができず、蕪村の独壇場という趣すらある。そして、蕪村自身、こういう句を得意としていて、また、好みの世界のものであったのであろう。そういう意味では、蕪村自身が、この句に長点印を付したことは十分に頷けるところのものである。
蕪村の自賛句(その二一)
一七一 春おしむ座主の聯句に召されけり
本間本所収。平点より上で長点よりした珍重の印のある句。前句(その二〇)と同時の頃の作。「座主」とは一山の寺務を総理する者。また、比叡山の天台座主の専称のこと。この句は「春ををしむ座主の聯句や花のもと」という句形のものもある。句意は「天台座主の催された惜春の連句の会に連衆として召された。その光栄はもとより、近江・山城の春景を眼下にした眺望はいかにも春を惜しむにふさわしく、詩情そぞろなるものがある」(『蕪村全集(一)』)。蕪村が実際に天台座主の興行の連句会に召されたのかどうかは不明。この句は蕪村か亡くなる一年前の作なのであるが、蕪村は晩成の人で、この年には夜半亭三世となる几董との文音による両吟歌仙に取り組むなど、画・俳二道にわたって絶頂期にあり、その二道においてその名をとどろかさせたいた頃で、実際にこういうことがあったのかもしれない。しかし、前句(その二〇)の「同車の君のささめごと」といい、この掲出句の「座主の連句」といい、いかにも、蕪村の世界のものという印象とともに、やはり、蕪村は江戸時代の京都を中心にして活躍した人という印象を深くする。
蕪村の自賛句(その二二)
一九八 海棠や白粉(おしろい)に紅をあやまてる
本間本所収。長点句。安永四年(一七七五)、蕪村六十歳のときの作。海棠は「睡れる花」という異名を持つ。この異名は楊貴妃の故事に由来があるとされている。この句も海棠を見ての嘱目的な句ではなく、その楊貴妃の故事を背景としての見立ての作句といえる。句意は「うつむきがちに桜よりも濃くほんのりと紅を含んだ海棠の花。酒に酔った楊貴妃のしどけない寝起きの化粧のように、白粉と誤って紅をは刷いたのか」(『蕪村全集(一)』)。
蕪村の時代はともかくとして、海棠を見て楊貴妃の故事に結びつけて作句するということは、現代においてはほとんどなさなれないことであろう。掲出句の視点の「酒に酔った楊貴妃のしどけない寝起きの化粧のように、白粉と誤って紅をは刷いたのか」ということになると、どちらかというと滑稽句に近いものになる。そして、その滑稽味を蕪村は佳としているのであろうが、同時の頃の作の「遅き日のつもりて遠きむかし哉」に比すると、後者に軍配をあげざるを得ないのである。そして、几董編の『蕪村句集』には掲出句は収載されていないが、後者の句は収載されていて、夜半亭二世・蕪村と夜半亭三世・蕪村との選句姿勢の違いなども感知されるのである。
