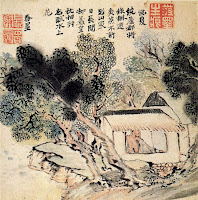若き日の蕪村(七)

(七十六)
ここで、蕪村の絵画の方面について触れてみたい。そもそも、与謝蕪村の出発点は、俳諧師を目指したものなのか、それとも、絵画師を目指したものなのかどうか、これもまた謎である。明治に入って、正岡子規の、いわゆる、俳人・蕪村の再発見以前は、どちらかというと、画人・蕪村という趣であった。すなわち、蕪村は大雅とともに日本の文人画(南画)の大成者として日本画壇の一方の雄として燦然と輝く存在であった。次のアドレスの「日本美術史ノート 江戸中期の絵画 南画 大雅と蕪村」に、その生涯の年譜が紹介されているが、その書画を中心として抜粋すると下記のとおりとなる。
http://www.linkclub.or.jp/~qingxia/cpaint/nihon24.html
(書画)
元文二(一七三七)京から江戸に戻った夜半亭宋阿 (早野巴人)の内弟子となる。画にも親しむ。 服部南郭の講義にも列席。
寛保二(一七四二)恩師宋阿に死別、同門下総結城の雁宕 (がんとう) に身を寄せる。約十年奥羽などを旅の生活。この頃、結城、下館等に画。
延享一(一七四四)宇都宮で処女句集『歳旦帖』、初めて蕪村の号。
宝暦一(一七五一)宋阿門流の多い京に上る。俳諧より画業に専心。
(1754-57)丹後宮津(与謝郡、母の墓)に滞在。絵による生活も安定。結婚、一女をもうける。四明,朝滄の号で多彩な様式を試みる。 彭城百川に学ぶ。 狩野派・大和絵系、中国絵画や版本類を研究し自己の画風を形成。
宝暦九(一七五九)沈南蘋を学ぶ。 趙居の落款。
宝暦十(一七六〇)この頃、名を長庚、字を春星、また与謝氏を称する。
(1763-66)山水画の屏風を講組織のために盛んに描く。
(1766-68)二度讃岐滞在。俳諧にも次第に熱意。丸亀妙法寺《蘇鉄図》。
明和七(一七七〇)夜半亭二世、宗匠に。
(1771)春、歳旦帖『明和辛卯春』を出す。〈離俗論〉。詩(漢詩)・画・俳一致、俳諧の理想境に至る方法。《十便十宜図》池大雅合作。〈十宜図〉。
(1772)安永年間、画の大成期。
(1776)洛東金福寺に芭蕉庵を再興。この頃〈俳諧物の草画〉俳画の完成。
(1778)以降晩年 謝寅 (しやいん) 落款。芭蕉紀行図巻、屏風を多作。
(1779)芭蕉紀行図巻、屏風を多作。
天明三(一七八三)暁台主催の芭蕉百回忌、取越追善俳諧興行。九月宇治田原にきのこ狩に行ったのち病に倒れる。十二月二十五日没、金福寺に葬られる。
(七十七)
この年譜の「元文二(一七三七) 京から江戸に戻った夜半亭宋阿 (早野巴人)の内弟子となる。画にも親しむ。 服部南郭の講義にも列席」ということは、現に、柿衛文庫に所蔵されている「俳仙群会図」(画像・下記アドレス)の画賛「此俳仙群会の図は、元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして、ここに四十有余年に及べり。されば其稚拙今更恥べし。なんぞ烏有とならずや」(この俳仙群会の図は、元文の昔、私が若い時描いたもので、それからもう四十年あまりもたってしまった。だからその下手な筆づかいは今さら恥ずかしい。どうしても焼けなくなってしまわなかったのだろうか)なども念頭にあってのことだろう。この「俳仙群会図」について、山下一海氏は、「古今の俳人から、宗鑑・守武・長頭丸(貞徳)・貞室・梅翁(宗因)・任口上人・芭蕉・其角・嵐雪・支考・鬼貫・八千代・園女・宋阿の十四人を選びその像を描いて朝滄と書名し、その上段に任口以外の十三人の代表句を一句ずつ記している。四十余年後の蕪村が、拙いものだから残っていない方がよかったといっているように、蕪村独自の表現とはなり得ていないにしても、簡素ながら丁寧な描出ぶりは、この時期の蕪村の画投への打ち込み方を十分に窺わせるものである」(『戯遊の俳人 与謝蕪村』)と記している。しかし、この初期の蕪村の傑作作品とされている「俳仙群会図」については、尾形仂氏らによって、「『朝滄』の落款から推して、四十代初頭の丹後時代の作」(『蕪村全集四』)と、元文時代(二十二歳~二十五歳の頃)のものではなく、宝暦元年(三十六歳)の京再帰後の、丹後時代(三十九歳~四十二歳の頃)の作とされ、蕪村の俳詩「北寿老仙をいたむ」の制作時期を巡っての論争と同じように、その制作時期については、「元文年間説」と「宝暦年間説」とが対立している。この作品を所蔵している「柿守文庫」は、下記の「参考」のとおり、「元文年間説」の記述なのであるか、やはり、その署名の「朝滄」、そして、「丹青不知老到」(白文方印)からして、ここは、尾形仂氏らの「宝暦年間説」(丹後時代)によるものと解したい。
http://hccweb6.bai.ne.jp/kakimori_bunko/shozo-buson.html
(参考)
蕪村(ぶそん・一七一六~一七八三)は文人画家として独自の画境を開きました。また、俳諧では「離俗」を理念に、高い教養と洗練された美意識をもって、写実的で浪慢的な俳諧を展開し、芭蕉亡き後の俳壇を導きました。本点は下段に14人の俳仙、宗鑑・守武・長頭丸(貞徳)・貞室・梅翁(宗因)・任口・芭蕉・其角・嵐雪・支考・鬼貫・八千代・園女・宋阿(巴人)の像を集め、中段に任口以外の13人の代表句を記しています。さらに上段には蕪村が後年になって求めに応じて書き加えた賛詞があり、それによると、「元文のむかし」、すなわち蕪村の21歳から24歳のころの作品で、本図が伝存する蕪村筆の絵画の中では最も初期のものであることがわかります。
(七十八)
この「俳仙群会図」については、「柿衛文庫」の創設者の岡田利兵衛氏の『俳画の美 蕪村・月渓』で、その解説を目にすることができる。その紹介の前に、先の「柿衛文庫」の紹介記事中の、岡田利兵衛こと岡本柿衛に関するものを参考までに以下に掲載をしておきたい。
http://hccweb6.bai.ne.jp/kakimori_bunko/okada-rihei.html
(参考)
岡田柿衞は明治二五年(一八九二)八月二七日、江戸時代から続く伊丹の酒造家、岡田正造の長男として生まれました。幼名は真三、二六歳のとき利兵衞(リへえ)を襲名。京都帝国大学文学部国文科卒業。梅花女子専門学校、聖心女子大学、橘女子大学などで教鞭をとるとともに、伊丹町長・市長職を務めました。 郷土の俳人、鬼貫(おにつら)に端を発する俳諧資料の収集は、俳諧史全般へと拡大。学術研究上必要な資料の蓄積を、現在の(財)柿衞文庫に遺しました。『鬼貫全集』『俳画の美』ほか著書多数。中でも『芭蕉の筆蹟』は芭蕉筆蹟学の礎を築いた名著。柿衞は号で、歴代の当主が愛でた岡田家の名木「台柿(だいがき)」を衞(まも)るの意を込めたもの。この柿の実は、文政一二年一〇月、頼山陽が母とともに伊丹を訪れた際、「剣菱」醸造元の坂上桐陰の酒席で、デザートに供され、山陽はあまりのうまさに感激したという逸話が残っています。そのとき、山陽はもう一つと所望しましたが、「岡田家に一本あるだけの柿なのであきらめてほしい」と断られたといいます。柿衞が岡田家伝来品に加え、独自の俳諧資料収集を思い立ったのは昭和一二年、鬼貫の短冊との出合いがきっかけでした。その後終戦前後の一〇年間は積極的に資料を集め、当時の様子を「俳人遺墨入手控」や「俳諧真蹟入庫品番付」に記録しています。番付は相撲好きの柿衞が、前年度手に入れた俳諧関係の真筆資料を相撲の番付に模して作成したもので、たとえば昭和二三年度の東の横綱として「西鶴自画賛十ニケ月」、西の大関として「鬼貫筆にょっぽりと秋の空なる富士の山の一行物」をあげています。柿衞は多趣味で知られ、洋鳥の飼育、写真撮影、高山植物の育成などにも熱中。洋鳥においては、山階芳麿(やましなよしまろ)ら九人で「鳥の会」を結成したり、千坪近い庭に禽舎『胡錦園(こきんえん)」を設けて飼育するほどでした。昭和五七年(一九八二)六月五日、伊丹で没。八九歳でした。柿衞は没するまで、現在の柿衞文庫、伊丹市立美術館、工芸センターの敷地内で暮らし、その家の一部は平成四年一月、「旧岡田家住宅」(店舗・酒蔵)として国の指定文化財となり、阪神・淡路大震災で大きな被害を受けたため、解体修理されています。山陽の愛した台柿(二世)は、柿衞文庫館の庭園で毎秋、独特の実をたくさんつけています。
(七十九)
さて、「柿衛文庫」の創設者の岡田利兵衛氏の『俳画の美 蕪村・月渓』での、「俳仙群会図」の解説は次のとおりである。
右の大きさ(画 竪三五センチ 横三七センチ 全書画竪 八七センチ)の絹本に十四人の俳仙、すなわち宗鑑・守武・長頭丸(貞徳)・貞室・梅翁(宗因)・任口・芭蕉・其角・嵐雪・支考・鬼貫・八千代・園女と宋阿(巴人)の像を集めてえがいている。特に宋阿は蕪村の師であるので加えたもので、揮毫の時点においては健在であったから迫真の像であると思われる。着彩で精密な描写は大和絵風の筆致で、のちの蕪村画風とは甚だ異色のものである。これは蕪村が絵修業中で、まだ進むべき方途が定まっていなかったからであろう。しかし細かい線の強さ、人物の眼光に後年の画風の萌芽を見出すことができる。
中段に別の絹地に左の句がかかる。
元日や神代のこともおもハるゝ (守武)
鳳凰も出よのとけきとりのこし (長頭丸)
これハこれハ(註・送り記号)とはかり花のよしのやま(貞室)
手をついで歌申上る蛙かな (宗鑑)
ほとゝきすいかに鬼神もたしかに聞け (梅翁)
古池や蛙飛こむ水の音 (芭蕉)
桂男懐にも入や閏の月 (八千代)
古暦ほしき人にはまひらせむ (嵐雪)
いなつまやきのふハひかしけふは西 (其角)
はつれはつれ(註・送り記号)あハにも似さるすゝき哉(園女)
不二の山に小さくもなき月しかな (鬼貫)
かれたかとおもふたにさてうめの花 (支考)
こよひしも黒きもの有けふの月 (宋阿)
任口上人の句ハわすれたり
平安 蕪邨書 謝長庚印 謝春星印
さらに上段に左記の句文か貼付される。これは紙本である。
此俳仙群会の図ハ、元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして、こゝに四十有余年に及へり。されハ其稚拙今更恥へし。なんそ烏有とならすや。今又是に讃詞を加へよといふ。固辞すれともゆるさす。すなはち筆を洛下の夜半亭にとる。
花散月落て文こゝにあらありかたや
天明壬寅春三月
六十七翁 蕪村書 謝長庚印 潑墨生痕印
この三部は三時期に別々にかかれたもの。上段は紙本で明らかに区分されるが、中段と下段はどちらも絹本であってやや紛らわしいかもしれないが絹の時代色が違うのと、謝長庚・謝春星の印記が捺され、この号は宝暦末から使用されるから、これから見て区分は明白である。上段の文意によってもそのことがわかる。
ここで最も重大なことは上段に「元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして、こゝに四十有余年」と自ら記している点である。これは絵が元文期・・・蕪村二十一歳から二十四歳・・・に揮毫されたことを立証している。すなわち現に伝存する蕪村筆の絵画
中の最も早期にかかれたものであり、その点、甚だ貴重な画蹟といわねばならぬ。それに四十有余年後の天明二年に賛を加えよといわれて、困ったが自筆に相違ないので恥じながら加賛したのである。
この画の落款は朝滄である。この号はつづく結城時代から丹後期まで用いられるものである。また印記の「丹青不知老到」という遊印であるが、この印章は初期に屡々款印に用いられている。すなわち下段の画は元文、中段の句は安永初頭(推定)、上段は天明二年の作である。
本点上段の句文は『蕪村翁文集』(忍雪・其成編 文化十三年刊)に登載している。原典と異なるところは、句文の前に三行の詞書を加え、本文句中に「何そ・則・斯」の三カ所を漢字に変えている。詞書は下段・中段をはずしたために説明が必要で添付したものであり、原典仮名を改めたのは筆写の手数をはぶくためで、どちらも原典を改変した作為の責めは負わねばならぬ。本点は蕪村最古の絵画として意義深いものであるからカラーで掲げた。
(八十)
この「俳仙群会図」は、この岡田利兵衛氏の解説にあるとおり、「下段の画は元文、中段の句は安永初頭(推定)、上段は天明二年の作」と三時期に別々にかかれたものであるということと、もし、この下段の画が「元文」年間のものとすると、この岡田氏の指摘のとおり、「蕪村最古の絵画」として誠に意義深いものということになろう。ここで、この三時期の、署名と印章などを見てみると、上段は「天明壬寅春三月 六十七翁 蕪村書 謝長庚印 潑墨生痕印」、中段は「平安 蕪邨書 謝長庚印 謝春星印」、そして、下段の画は「朝滄写 丹青不知老到印」ということになる。この上段の天明期の「謝長庚印 溌墨生痕印」は、蕪村の最高傑作の一つとされている、国宝「十宣図」などで見られるもので、「六十七翁 蕪村書」も、天明三年の「恵比寿図」の「六十八翁蕪村写」とその例を見ることができる。中段の安永期の「謝長庚印 謝春星印」は、これまた、重要文化財の「峨嵋露頂図」などに見られるもので、その「平安 謝蕪邨」の「平安」は「洛東芭蕉菴再興記」、そして、「謝蕪邨」についても、『夜半楽』などにその例を見ることができる(この『夜半楽』の二つの署名の「謝蕪邨」と「宰鳥校」については先に触れた)。問題は、この下段の元文期の画の「朝滄写 丹青不知老到印」なのである。この元文期というのは、蕪村の前号の「宰町・宰鳥」期のものであって、そもそも比肩するものなく、わずかに、元文三年の版本挿絵図の「鎌倉誂物」自画賛(『卯月庭訓』所収)から推測する程度と極めて限られてしまうのである(この「鎌倉誂物」自画賛についても先に触れた)。さらに、この元文期に続く、巴人亡き後の、寛保・延享・寛延時代の、いわゆる、結城・下館・宇都宮を中心とする北関東出遊時代の「絵画・俳画・版本挿絵図・遺墨」類などにおいて、「朝滄写」との落款ものは見当たらず(「朝滄印」は目にすることができるが、落款は「四明」が多い)、また、この「丹青不知老到印」は、丹後時代の傑作作品の一つとされている六曲屏風一双「山水図」(寧楽美術館蔵)などに見られるもので、この丹後期以前の作品ではまずお目にかかれないものの一つであろう。そもそも、この「朝滄」という号は、英一蝶の号の「朝湖」に由来があるとされている(河東碧梧桐『画人蕪村』)。そして、この英一蝶は俳号を睦雲・和央といい、蕪村の俳諧の師である宋阿(早野巴人)と同じく其角門の俳諧師でもあった。
後に、画・俳二道を極めることとなる蕪村が、そのスタートにあたってこの英一蝶を目標に置いていたということは想像するに難くない。その英一蝶の影響を察知できるものとしては、これまた、丹後時代の傑作画である「祇園祭礼図(別名・田楽茶屋図屏風)」(落款「嚢道人蕪村」、印「朝滄(白文方印)」・「四名山人(朱文方印)」)などがあげられるであろう。画人・蕪村の絵画として今に残っている最初の頃の作は、巴人亡き後(寛保二年)の、北関東出遊時代の下館(中村風篁家)・結城(弘経寺)に所蔵されているものが、その「蕪村最古の絵画」ということになろう。それより以前に、この「俳仙群会図」が描かれたものとすると、蕪村の丹後時代以前の全半生というものは、ことごとくその歴史を塗り替える必要があろう。即ち、蕪村が江戸に出てきて宋阿門に入ったとされる元文二年(蕪村・二十二歳)当時に、これだけの絵画作品を残していたということは、それ以前に、相当の絵画関連の知識・技能・経験を積んだものということが推測され、蕪村の未だに謎の部分とされている、蕪村の出生の年の享保元年(一七一六年)から江戸に出てきた元文二年(一七三七年)の謎の一角がほの見えてくるという感じでなくもないのである。ここで、
画・俳二道の画を中心として、その蕪村の謎の部分について触れてみたい。
(八十一)
蕪村が江戸に出てきて宋阿門に入門する元文二年(蕪村、二十二歳)以前のことについては、蕪村自身多くを語らず、逆に、それを隠し続けて、その生涯を終わったという印象を深くする。晩年、「春風馬堤曲」に関連しての蕪村書簡中(年次不明二月二十三日付け柳女・賀瑞宛て書簡)に、「馬堤は毛馬塘(つつみ)也。則余が故園也」とし、「余幼童之時、春色清和の日には、必(かならず)友だちと此(この)堤上にのぼりて遊び候」と記しており、摂津国東成郡毛馬村(大阪市豊島区毛馬町)に生まれたということは、少なくとも、蕪村の意識下にはあったように推測される。この毛馬村説についても確たる確証があるわけではなく、その他に、摂津の天王寺村(大阪市天王寺地区)としたり、丹後の与謝(京都府与謝郡)とする説など実体は謎に隠されているというのがその真相である。何時生まれたかについても、これまた真相は藪の中で、明治十五年(一八八二年)に寺村百池の孫百僊が、蕪村百回忌・百池五十回忌を記念して金福寺境内に建立した碑文などにより、享保元年(一七一六)の生まれという推測がなされている。その碑文では天王寺説をとっており、この碑文の内容自体あやふやのところが多いのであるが、「本姓谷口氏は母方の姓」で「宝暦十年頃から与謝氏を名のる」というのが、その出生に関連するものである。さらに、この出生に関連するものとして、夜半亭二世与謝蕪村の後を継いで、夜半亭三世となる高井几董がその臨終を記録した「夜半翁終焉記」(草稿を含めて)が、蕪村出生の謎をさらに深い霧の中に追いやっている。それは、その草稿の段階においては、「難波津の辺りちかき村長の家に生ひ出て」と記し、さらに、その「村長」を「郷民」と改め、さらにそれを削って、「ただ浪花江ちかきあたりに生ひたち」として、それを定稿としているという事実である。これらのことから、「父は村長で、母はその正妻ではなく、使用人か妾ではなかったか」という説すらまかり通っているのだが、ことさらにこれらの謎をあばきたてて、それらを白日下のもとに明らかにするということは、行き過ぎのきらいもあるし、土台不可能なことという思いを深くする。そういう認識下に立っても、蕪村没後二十三年たった文化三年(一八〇六年)に大阪で刊行され、当時の文学者の逸話を幾つか伝えている田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』の「夫(それ)蕪村は父祖の家産を破敗し、身を洒々落々の域に置いて」との逸話は、やはり当時の蕪村の一端を物語るものとして、やはり記録に止めておく必要があるように思われる。
なお、大阪市(都島区)の「与謝蕪村と都島」のアドレスは次のとおりである。
http://www.city.osaka.jp/miyakojima/spot/yd_yosa/index.html
(八十二)
蕪村が出生した享保元年というのは、八代将軍吉宗が、いわゆる「享保改革」といわれる大改革に乗り出したその年に当たる。当時の徳川幕府というのは経済的にどん底の状態にあり、倹約令を発し続け、さらに、追い打ちをかけるように、特に、農村からの収奪を強化することによって、その改革を進めようとした。それらの改革は時代の空気を陰鬱なものとし、あまつさえ、享保十七年(一七三二年)には、山陽・南海・西海・畿内の西国地方の各地では長雨と蝗の襲来により、減収四万石ともいわれている大凶作に見舞われていた。米価は高騰し、多数の餓死者が出て、各地で強訴や一揆が多発し、その翌年には、江戸をはじめ各地で打ち壊し運動が起こり、騒然とした風潮であった。そのような何もかも変革するような時代風潮の中にあって、田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』でいう「夫(それ)蕪村は父祖の家産を破敗し、身を洒々落々の域に置いて」という逸話は、単に、蕪村の個人的な遊蕩三昧によって「家産を破敗」したというよりも、この経済環境の激変の高波をもろに引っ被ったその結果であるということが、その真相のように思われる。その「身を洒々落々の域に置いて」ということについては、高井几董の「夜半翁終焉記」に出てくる「此翁(註・蕪村)無下にいとけなきより画を好み」、はたまた、「弱冠の比(ころ)より俳諧に耽り」ということと裏返しのことなのかもしれない。しかし、単なる、「画を好み」・「俳諧に耽り」の結果で、二度と故郷に足を踏み入れることが出来なくなったほどの、世間体を憚る「父祖の家産を破敗」したいうことは、どう考えても不自然なところがある。このことを一歩進めて、蕪村が住んでいた全村が、あるいは、その近隣の全域が「破敗」し、蕪村は文字とおり二度と再び「返るべき故郷」を喪失してしまったという理解の方が、より自然のようにも思われてくるのである。もし、そのような推測が許されるならば、蕪村は、享保十七年の近畿一帯の大飢饉に関連して、当時のその地方の人達が辿ったと同じように、当時の飢饉者の多くかそうしたように、誰一人身よりのない江戸へと移り住んだ、その理由がはっきりしてくる。従来、蕪村が江戸に出てきたのは、享保二十年(一七三五年)頃とされていたが、蕪村の前号の「宰鳥・宰町」以前に「西鳥」と号していたのではないかということに関連して、享保十七年(一七三二年)頃に出てきたのではないかとの見方もなされてきており、あながち、享保十七年の大飢饉に関連して江戸に流入してきたということも、有力な一つの見方であるということは言えそうである。しかし、真相は依然として藪の中であることには変わりはない。なお、享保十七年の大飢饉関連のアドレスは次のとおりである。
(飢饉・享保の大飢饉)
http://www.tabiken.com/history/doc/E/E147C100.HTM
(人権関連の一揆など)
http://www.can-chan.com/jinken/jinken-rekishi.html
(八十三)
蕪村伝記のスタンダードな『戯遊の俳人与謝蕪村』(山下一海著)の田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』関連の記述は次のとおりである。
○蕪村没後二十三年たった文化三年(一八〇六)に大阪で刊行され、文学者の逸話をいくつか伝えている田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』には、「夫(それ)蕪村は父祖の家産を破敗し、身を洒々落々の域に置いて」とある。これも確証はないが、信じたくなる記事である。正妻の子ではなかったにしても、男子であるからには、家督を相続したということもあったのだろう。いつ父が死んだのか、それはわからない。母も幼い頃に先立ったらしい。安永六年(一七七七)に行われた『新花摘』の夏行(げぎょう)を、母の五十回忌追善のものとする説によると、母が亡くなったのは蕪村十三歳のときである。蕪村が家督を継いで家産を蕩尽するまでは、そう長いことではなかっただろう。それは大都市近郊農村の悲劇であった。都市の商人に農地を買いあさられ、土地を手放すかわりに金が入ってくる。そこで農村型の経済生活から都市型のそれに切り替えていかなければならないところだが、農村はそういった情勢に順応できなかったのだろう。せっかく父から譲られた家屋敷も手放さなければならないことになったが、あるいはそこに、父に対する蕪村の反抗の気持ちが多少はあったのかもしれない。それが破産を回避する努力をにぶらせ、破滅の到来をいささか早める結果になったということも、あるいはあったことだろう。
多かれ少なかれ、蕪村伝記の記述は上記のようなものであるが、上記の「都市近郊農村の悲劇」は当時の時代風潮であり、その時代風潮とあわせ、享保の時代特有の。改革の嵐と大飢饉という異常事態の発生ということは、やはり特記しておく必要があろう。また、上記の記述で、「母が亡くなっのは蕪村が十三歳のとき」ということに関連して、当時は十五歳で元服するのが通常であったろうから、蕪村の家督相続というのは、その元服以後と通常考えられるし、この十五歳から十七歳のときの享保の大飢饉にかけてが、蕪村にとっては大きな曲がり角であったということも特記しておく必要があろう。さらに、蕪村が母を失ったとされる享保十三年(一七二八)の一年前の享保十二年に、蕪村の俳諧の師となる早野巴人(宋阿)が江戸を去って大阪に赴き、さらに京都に上り、十年ほど居住するという、このこともやはり蕪村伝記の記述に当たっては必要不可欠のところのものであろう。
(八十四)
『戯遊の俳人与謝蕪村』(山下一海著)では、蕪村が江戸に出てきたことについて、次のように記述している。
○親もなく家もない故郷にとどまっていることはできない。あるいは、蕪村にとって故郷毛馬村は、積極的な意味で、とどまっていたくないところであったのかもしれない。蕪村のような生い立ちの人間にとって、故郷の家が消滅することは、さっぱりと心地よいことでもあったのだろう。しかしそれだけに、故郷の思いは、かえって深く、心の底に沈殿した。そうして生涯にわたって、そこから沸々と発酵するものがあった。しかしその後、ほんのすぐそばを通っても、蕪村は一度も故郷に足を踏み入れていない。そこに蕪村と故郷の特別の関係が窺われるように思われる。当時の多くの人がそうであったように、そういう事情で故郷を離れたとき目ざすところは、京や大坂ではない。新しい土地江戸である。江戸開府以来百年以上たっているけれども、依然として江戸は京・大坂とは違った新興都市であり、また百年以上もたっているだけに、徳川将軍のお膝元としての権威は確立していた。江戸は当時の青年の気をそそるに足る唯一の都会であった。蕪村は江戸に出て何をしようという方策を、はじめにはっきりと立てていたわけではないだろう。江戸に出れば何とかなる。とにかく江戸に出た。享保末年、二十歳のころのことである。江戸に出ても、生活の方途は定まっていなかったが、俳諧や絵画については、すでにかなりの関心を持っていたようである。あるいはその関係で、江戸出府の手引きをした人物があったのかもしれない。蕪村没後十九年目の享和二年(一八〇二)に刊行された大江丸の『はいかい袋』によると、蕪村は江戸に出て、はじめ内田沾山(せんざん)に学び、ついで早野巴人の門弟になったという。巴人入門は確かだが、沾山入門のことは確実な資料が見当たらないので、いささか疑わしい。ほかに足立来川(らいせん)に学び、西鳥と号したとする説もあるが、今はほとんど否定されている。
上記の記述で、蕪村が故郷(大阪近郊の毛馬村)を離れ、当時の経済第一の都市・大阪や日本文化の中心都市・京都ではなく、それらの都市に比して新興都市の江戸を目指した指摘については説得力がある。と同時に、「俳諧や絵画については、すでにかなりの関心を持っていたようである。あるいはその関係で、江戸出府の手引きをした人物があったのかもしれない」ということについては、当時の江戸俳壇にその名を留めている、足立来川、内田沾山はたまた早野巴人らに入門するということは、それ相応のルートなり縁というものがあると思われるのだが、その手引きした人物が誰なのかは、これは全くの霧の中である。ただ、注目すべきことがらとして、巴人と親交があり、当時、巴人・百里と並んで享保俳壇の三羽烏の一人とされていた琴風(きんぷう:寛文七年・一六六七~享保十一年・一七二六。生玉氏)が蕪村と同郷の大阪摂津東成郡の人で、その接点というのも選択肢の一つとしてはあげられるであろう。また、当時の大阪・京都の上方俳壇に大きな影響力を及ぼしていた俳人は、松木淡々(たんたん:延宝二年・一六五四~宝暦十一年・一七六一。初号、因角、のち謂北。大阪の人。江戸に出て、初め不角門、のち其角門。巴人と同門。上京して、半時庵を営む。その後、大阪に帰り、上方俳壇に絶大な門戸を張る)で、この淡々門で、のちに、淡々の号・謂北を継ぐ麦天(ばくてん:元禄十六年・一七〇三~宝暦五年・一七五五。右江氏。別号・時々庵。江戸に出て二世青蛾門。享保頃秋田遊歴。元文二年・一七三七に謂北に改号)と蕪村とは親交があり、その麦天の師の淡々と蕪村との接点も注目すべきものがあろう(享保十二年・一七二七、巴人が江戸から京に移り住むのは、当時親交のあった百里・琴風が亡くなり、この其角門で親交の深かった淡々が大きく関与している)。また、巴人門の宋屋(そうおく:元禄元年・一六八八~明和三年・一七六六。望月氏。別号、百葉泉・富鈴房など。京都の人)も巴人門に入る前から蕪村との親交があったものかどうかなども検討に値する一つであろう。なお、上記の山下一海氏のものでは、「巴人入門は確かだが、沾山入門のことは確実な資料が見当たらないので、いささか疑わしい。ほかに足立来川(らいせん)に学び、西鳥と号したとする説もあるが、今はほとんど否定されている」ということについても、「沾山・来川との関係、宰町以前の西鳥を号していたかどうか」などについては、肯定的に解して、その範囲を広めて置いた方が、謎の多い蕪村の解明にはより必要のようにも思われる。
(八十五)
寛保三年(一七四三)の宋屋編『西の奥』(宋阿追善集)に当時江戸に居た蕪村は「東武
宰鳥」の号で、「我泪古くはあれど泉かな」の句を寄せる。その前書きに、「宋阿の翁、このとし比(ごろ)、予が孤独なるを拾ひたすけて、枯乳の慈恵のふかゝりも(以下、略)」と記しているが、「枯乳の慈恵」とは、乳を枯らすほどの愛情を受けたということであろうから、この記述が江戸での流寓時代のことなのかどうか、その「予が孤独なるを拾ひたすけて」と重ね合わせると、宋阿の享保十二年(一七二七)から元文二年(一七三七)までの京都滞在中の早い時期に、宋阿と蕪村との出会いがあったとしても、決しておかしいということでもなかろう。まして、蕪村が十五歳の頃、元服して家督を相続し、そして、享保十七年(一七三二)の十七歳の頃、大飢饉に遭遇し、故郷を棄てざるを得ないような環境の激変に遭遇したと仮定すると、この方がその後の宋阿と蕪村との関係からしてより自然のようにも思われるのである。尾形仂氏は、「巴人が江戸に帰ったときにいっしょに江戸へ下ったんじゃないかと考えることさえできるんじゃないかと思っているのですが」(「国文学解釈と鑑賞」昭和五三・三)との随分と回りくどい対談記録(森本哲郎氏との「蕪村・その人と芸術」)を残しているのだが、少なくとも、宋阿が江戸に再帰した元文二年に、その宋阿の所にいきなり入門するという従来の多くの考え方よりも、より自然のように思われるのである。一歩譲って、「巴人が江戸に帰ったときにいっしょに江戸へ下った」ということまでは言及せずに、、ということは、あながち、無理な推測ではなかろう。このことは、蕪村が、宝暦元年(一七五一)に、十年余に及ぶ関東での生活に見切りをつけ、京都に再帰することとも符合し、その再帰がごく自然なことに照らしても、そのような推測を十分に許容するものと思えるのである。これらのことに関して、上述の尾形仂氏と森本哲郎氏との対談において、尾形仂氏の「蕪村の京都時代ということの推測」について、「しかしそれはありうることじゃないですか。というのは、彼は関東から京都へ行くわけですが、入洛してすぐに居を定めている。むろん、はしめは間借りだったようですけれども、京都には知人もいたらしいし土地カンもあったように思えます」と応じ、この両者とも、「蕪村は生まれ故郷の大阪を離れ、京都に住んでいたことがあり、少なくとも、巴人の十年に及ぶ京都滞在中に蕪村は巴人と面識があった」という認識は持っているいるように受け取れるのである。
(八十六)
「国文学解釈と鑑賞(昭和五三・三))所収の「蕪村・その人と芸術」(尾形仂・森本哲郎対談)に次のような興味の惹かれる箇所がある。
尾形 ええ。もう一つ京都との結びつきを考えさせられるのは、岡田先生の『俳画の美』という本がございますね、あの中に、京都から池田に下って明和二年に亡くなった桃田伊信という絵師がいて、蕪村が童幼のころ、この伊信について絵の手ほどきを受けたらしいことを、蕪村の三回忌に池田の門人田福が書いているということが紹介されていまして、そうすると、蕪村が少年時代を京都で過ごしたという可能性がまた出てきたことになります。
森本 私もあれを読んで、そうなのか、と思ったんですけれども・・・。池田とはずいぶん関係があったようですね。
尾形 そうですね。後に月居や月渓を池田に紹介したりしているくらいですものね。そもそも田福が百池と親戚で、京都の本店と池田の出店との間を往き来していたところから縁ができたものでしょう。
森本 「池田から炭くれし春の寒さ哉」という句がありますし。その絵の先生というのは後年までずっと?
尾形 明和二年ごろ、つまり伊信の最晩年、蕪村が池田へ下ったとき再会して、昔を語り合ったというのですから、ずっとというわけではなかったのでしょう。ともかく、もと京都にいた伊信に十歳前後のとき絵の手ほどきを受けたのだとすれば、蕪村は何かの事情で郷里を離れ京都へ出て来て、あるいは学僕というような形で伊信なり、巴人なりに師事したという想像もできなくはありませんね。
これらの対談の箇所は、「蕪村が少年時代を京都で過ごしたという可能性」があるということに関連するものなのであるが、そのこととあわせ、「蕪村はもと京都にいた(桃田)伊信に十歳前後のとき絵の手ほどきを受けた」ことがあるという事実もまた、当時の蕪村を知る上では貴重な情報と思われるのである。先に、蕪村絵画の若描きの頃の落款の「朝滄」ということに関連して、その「朝滄」という号は、蕪村が目標とした画家の一人とも思われる英一蝶の号の一つの「朝湖」に由来するという河東碧梧桐氏のものなどについて触れた。この蕪村と同じく大阪出身の英一蝶は、蕪村が八歳のとき、享保八年(一七二七)に江戸で亡くなっているが、そもそもは狩野派(京都狩野派)の画家で、そして、蕪村が少年時代に絵の手ほどきを受けたという京都の画家・桃田伊信も、当時の画家の多くがそうであったように、いずれかの狩野派の影響下にあったことは想像に難くないし、その意味では、先に触れた蕪村最古の絵画とされる「俳仙群会図」に英一蝶的なものが察知されることと関連して、興味がそそられる点なのである。
(八十七)
「国文学解釈と鑑賞(昭和五三・三))所収の「蕪村・その人と芸術」(尾形仂・森本哲郎対談)には、蕪村の初期絵画の落款の「四明・朝滄」について、次のような箇所がある。
尾形 それから関東に出てくる経緯についてもわかりませんですね。大正十年ごろ出た武藤山治さんの『蕪村画集』というのがございますね。あれに、関東時代から丹後時代にかけて使った四明・朝滄という画号について、四明は比叡山で、朝滄は琵琶湖を意味するという説明が付けられているんです。そうすると蕪村は京都から関東へ出て来たんじゃないか。まあ生まれたのは毛馬だとしても、京都で幼年時代を送って、そして関東へ出てきたんではないだろうか。つまり自分は、大阪生まれだけれども京都人であるという意識があって、そうした号をつけたのではないだろうかなどと推測してみたこともあったんですけれども。しかし、四明が天台、つまり比叡山であるということはよろしいんですけれども、朝滄が琵琶湖だということは、ちょつといろいろと探しても出てこないんですね。字引を引くと、朝滄は、波が集まるという意味だそうですから、なにも琵琶湖でなくて、淀川の下流でも十分意味が通ずるわけなんです。けれども、今度ははたして淀川の下流の毛馬堤から比叡山が見えるかどうか、という疑問になってきましてね。それから戦前に、正木瓜村というかたがいらしゃって、『蕪村と毛馬』という本を書いていらしゃいましたが、あの方にお目にかかりまして伺ってみたんですが、そうすると、自分の子どものころにはたしかに見えたというんです。今からではぜんぜん想像もできないんですけれども、毛馬の堤から朝夕に比叡山が眺められるなら四明と名のってもおかしくないわけで、それで蕪村の京都時代というのことを推測したのが、いっぺんに消えてしまったわけなんですけれども。
蕪村の元文年間(一七三六~一七四一)、寛保(一七四一~)から寛延(一七四八~)にかけての落款は、「朝滄・子漢・浪華四明・四明・浪華長堤四明・浪華長堤四名山人」などである。このうち、四明が主号のようで、次いで、朝滄、この朝滄は落款とともに印章に用いられており、この印章は、関東出遊時代と後の丹後時代とは異なっていて、先に触れた「俳仙群会図」のものなどについては、関東出遊時代のものではなく、丹後時代のそれではないかということについては、先に触れた。それにあわせ、河東碧梧桐の『画人蕪村』では、この四明については、比叡山に由来があり、朝滄については、英一蝶の朝湖に由来があるということについても、先に触れた。そして、この「子漢」については、別に、「魚君」の号も用いているものもあり、屈原の「漁夫辞」の「滄浪ノ水清(す)マバ」などに由来があり「水に因んでのもの」(淀川に因んでのもの)と「子は午前零時、漢は天の川」(夜の連想に因るもの)との両意のものなどを目にすることができる(仁枝忠著『俳文学と漢文学』所収「蕪村雅号考」)。いずれにしろ、四明は比叡山の最高峰の四明山に由来がある「山」、そして、朝滄は、英一蝶の「朝湖」、あるいは、「琵琶湖」・「淀川」・「宇治川」(「木津川」・「桂川」と合流し「淀川」となる)などに由来がある「川」に関連があるものと解しておきたい(「子漢」についても、初期の落款については、滄浪などの水に由来があるものと解せられるが、後の「春星」などの号に鑑みて、「真夜中の銀漢(天の川)」いう理解に留めておきたい)。その上で、上述の尾形仂氏のものに接すると、その「四明」といい「朝滄」といい、これは朝な夕なに生まれ故郷で目にしていた山・川の「比叡山」であり「淀川」という思いを強くする。とすれば、「浪華四明」・「浪華長堤四明」・「浪華長堤四名山人」などの落款も、消そうとして消せない母郷への想いの一端を語っているもののように思われる。と同時に、全く抹殺したいようなことならば、これらの痕跡すら留めておかないであろうから、これは蕪村個人にとっての何らかの心の奥底に沈殿している「故郷は遠くにありて想うもの」という想いなのであろう。ここで、山下一海氏の次のような記述を再掲しておきたい。
○親もなく家もない故郷にとどまっていることはできない。あるいは、蕪村にとって故郷毛馬村は、積極的な意味で、とどまっていたくないところであったのかもしれない。蕪村のような生い立ちの人間にとって、故郷の家が消滅することは、さっぱりと心地よいことでもあったのだろう。しかしそれだけに、故郷の思いは、かえって深く、心の底に沈殿した。そうして生涯にわたって、そこから沸々と発酵するものがあった。しかしその後、ほんのすぐそばを通っても、蕪村は一度も故郷に足を踏み入れていない。そこに蕪村と故郷の特別の関係が窺われるように思われる。
(八十八)
その他、「国文学解釈と鑑賞(昭和五三・三))所収の「蕪村・その人と芸術」(尾形仂・森本哲郎対談)で、注目すべきことなどについて記しておきたい。
尾形 内田沾山に師事したというのは、同時代の大江丸が言っていることですから、かなり尊重しなければいけませんけれども、巴人との関係のほうが濃厚ですし、その後も巴人の系統の人のところをずっと渡り歩いていますものね。巴人にはかなり長く師事していたんじゃないでしょうか。そうすると、巴人が京都にいた時代にすでに師事していたと考えることも想像としてはできなくないと・・・。
森本 蕪村は師の巴人について、『むかしを今』の序で、「いといと高き翁にてぞありける」というぐあいに、たいへん人格的に傾倒しておりますね。
尾形 そして父親のようにというんですから、かなり年齢の低い時代からついていたんじゃないかという感じがいたしますね。
このところの、蕪村が内田沾山に師事したということについては、大江丸の『俳諧袋』に記述されていることに由来するのだが、この大江丸は、蕪村より七歳若い大阪の人で、三都随一の飛脚にして、俳諧にも親しみ、淡々とも親交があり、後に、蓼太門に入った。蕪村の後継者の几董との交友関係からして、この大江丸の記述はかなり信憑性の高いものなのであろう。この沾山は芭蕉・其角亡き後の江戸座の主流をなす、沾徳・沾州に連なる俳人で、巴人もまた沾徳・沾州と関係の深い俳人で、巴人が江戸に再帰する元文二年(一七三七)以前に、蕪村が江戸で沾山門に居て、巴人再帰後、巴人門に移ったということもあるのかもしれない。沾山は宝暦八年(一七五八)に没しており、その晩年には蕪村と親交のあった存義らが退座しており、蕪村のこの人への師事はいずれにしても短期間のものであったのであろう。
森本 蕪村は自ら嚢道人と称していますが、とにかく、何から何まで詩、画嚢に貯えて、それが将来花になったということなんでしょうね。しかし、私は彼の作品に接するたびに不思議に思うのですが、いったい彼はどこで、いつ、あのような幅広い教養を身につけたんでしょうね。たとえば、漢籍の素養、唐詩、宋詩についての知識、こういうものは江戸時代にどの程度普及しておったのですかね。最近、今田洋三氏が『江戸の本屋さん』という興味深い本を書かれましたが、当時、どのような本が、どのくらいの値段で、何部ぐらい出たのか、それを知らないと蕪村の教養の源泉も見当がつきませんね。
(中略)
尾形 先生というのは、儒学者に対する一般的な呼び方だそうですけれども、蕪村の場合、南郭先生と言っているのは、そうした一般的な意味でなくて、特殊、つまりかって南郭の講筵に列したか、あるいはすぐその近く、つまり南郭の講筵に列した人を知人に持っていたのではないかということが、かなり実証的に明らかにされてきました。(以下略)
ここのところの「嚢道人」の理解について、この嚢を乞食僧などの「頭陀袋」の意ではなく、「詩」嚢、「画」嚢の、それらを貯えておく「袋」の意と解する考え方は素直に受容ができる。また、蕪村の、単に、「画・俳」の二道だけではなく、広く、儒学者の服部南郭らの当時の他の分野との交流関係についても、密度の濃いものであったということについては、やはり特記しておく必要があるのであろう。
(八十九)
先に、蕪村最古の画作とされている「俳仙群会図」について触れた。その一番上段に書かれて画賛は次のとおりである。
※守武貞徳をはじめ、其角・嵐雪にいたりて、十四人の俳仙を画きてありけるに、賛詞をこはれて、此俳仙群会の図ハ、元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして、こゝに四十有余年に及へり。されハ其稚拙今更恥へし。なんそ烏有とならすや。今又是に讃詞を加へよといふ。固辞すれともゆるさす。すなはち筆を洛下の夜半亭にとる。
花散月落て文こゝにあらありかたや
天明壬寅春三月
六十七翁 蕪村書 謝長庚印 潑墨生痕印
この「俳仙群会図」について、『蕪村雑稿』(谷口謙著)で次のとおり紹介されている。
○天明壬寅は二年(一七八二年)で蕪村六十七歳の執筆。元文元年(一七三六年)~元文五年(一七四〇年)は蕪村二十歳から二十四歳。この蕪村の賛詞を信ずれば、現存する蕪村の画のなかで最古のものとなり、貴重な資料といえよう。岡田利兵衛氏は蕪村の加えた証詞をそのまま信用し、蕪村の若書きとして「全く後代の蕪村筆と異なり、漢画でもなければ土佐風でもない手法である。しかし子細に見ると着衣の皺法(しゅんぽう)、顔貌、眼ざしに後年の特色は、はやくも認めることができる。静のうちに活気ん゛ある表現である」(『俳人の書画美術五=蕪村』)と評している。これに対し「文学」誌五十九年十月号の座談会「蕪村…絵画と文学」で尾形仂氏は「朝滄」の落款、「丹青老ノ至ルヲ知ラズ」の印章が丹後時代だけに限って使われたものであることを重視し、丹後時代の作品ではないかと推定し、今迄は「俳仙群会図」を蕪村の画歴の最初としてきたが、置き換えた方がいいのではないかと提言している。これに答え佐々木丞平氏はこの画の衣の線を重視して、非常に決った線で、丹後時代になると例えば「三俳僧図」のように衣の線がかなり弛援してくる。つまり崩れを見せ、感覚的になっている。それでやはり「俳仙群会図」を丹後時代の作とするには、いささかためらいが残る、としている。
この昭和五十九年(一九八四)の座談会の後、平成十年(一九九八)に刊行された『蕪村全集六…絵画・遺墨』(佐々木丞平他編)においては、この「俳仙群会図」は「丹後滞在」時代の中に収録され、その佐々木丞平氏の「解説(蕪村画業の展開)」では「蕪村画業の最初のものとしては、「『俳諧卯月庭訓』(元文三年・一七三八)の中の一句に書き添えられた『鎌倉誂物』の自画賛で、版本の挿図であった」としている。やはり、この「俳仙群会図」は、その印章の「丹青不知老至」からすると「丹後時代」の作品と解すべきなのであろう。
もし、この作品を蕪村の天明二年(一七八二)の画賛のとおり元文年間のものとすると、この「俳仙群会図」の一人に描かれている、蕪村の師の宋阿(早野巴人)の像は在世中のものとなり、はなはだ興味がひかれるのところのものであるが、在世中の師の像を芭蕉らの他の俳仙と一緒にするという奇妙さ(同時に極めて俳諧的でもある)もあり、丹後時代の作品と解する方が、より妥当のようにも思われる。
(九十)
蕪村の『新花摘』に次のような一節がある。
「むかし余、蕉翁・晋子・雪中を一幅の絹に画(えが)キて賛をもとめければ、淡々、
もゝちどりいなおふ(ほ)せ鳥呼子どり
三俳仙の賛は古今淡々一人と云(いふ)べし。今しもつふさ日光の珠明といへるものゝ(の)家にお(を)さめもてり。」
この「もゝちどりいなおふ(ほ)せ鳥呼子どり」は、『延享廿歌仙』(延享二年刊)に収録されている松木淡々の門弟で蕪村と親交のあった謂北(麦天)の付句である。その句意は、「芭蕉・其角・嵐雪」の三俳人を古今伝授の三鳥「百千鳥・稲追鳥・呼子鳥」に擬したものということであろう。この句を当時の大物俳人の松木淡々が蕪村の画に賛をしたというのである。そして、この「三俳仙図」画は、下野の日光の隣の今市の富豪、斎藤珠明(三郎右衛門益信)の家に納めたというのである(現在、所在不明)。この賛をした淡々は宝暦十一年(一七六一)に八十八歳に没しており、この「三俳仙図」画が何時頃描かれものか定かではないが、蕪村はこの種の「俳仙図」画を多く手がけたということはいえそうである。こういう本格的な「俳仙図」画以外に、例えば、『其雪影』収録の「巴人像」などの版画・略画風のものは、いろいろな形(「俳仙帖・俳仙図・夜半翁俳僊帖など)で今に残されているが、この種のものは、河東碧梧桐氏によると殆ど偽作との鑑定をしている(潁原退蔵稿「蕪村三十六俳仙画)。これらのことに関して、潁原退蔵氏は、「碧氏の如き全面的抹殺説が出るのも、故なきではないわけである。しかし決して真蹟が絶無といふのではなかった。模写や偽作の背後には、その拠つた真蹟の存在が考へられもした。偽作が多く流布して居れば居る程、その間いくつかの真蹟がなほ存して居ることを思はしめるのである」(前掲書)としている。これらのことを背景として、先の「柿衛文庫」所蔵の「俳仙群会図」などは非常に貴重なものであると同時に、その制作時期の如何によっては、他の同種のものの作品に与える影響も決して少なくはないのである。そして、とりもなおさず、これらの「俳仙図」画が、蕪村の絵画の初期の頃に存するということは、蕪村の絵画のスタートが、これらの俳諧関係と大きく関係していたということも、十分に肯けるところのものであろう。
若き日の蕪村(八)

若き日の蕪村(八)
(九十一)
先に触れた、蕪村が十歳前後の頃に桃田伊信という絵師に絵の手ほどきを受けたということについて、「国文学解釈と鑑賞(昭和五三・三))所収の「蕪村・その人と芸術」(尾形仂・森本哲郎対談)で紹介されている『俳画の美』(岡田利兵衛著)のその箇所を見てみたい。
それは、天明五年(一七八五)十一月二十五日に、田福・月渓主催で蕪村三周忌追悼会を池田で催したときの刷り物にある次の田福の詞書によるものであった。
※夜半翁、むかし、池田なる余が仮居に相往来し、呉江の山水に心酔し、且、伊信(これのぶ)といへる画生に逢ひて、四十(よそ)とせふりし童遊を互に語りて留連せられしも、又二十(はた)とせ余りの昔になりぬ。ア丶我此(この)翁に随ひ遊ぶ事久し。(以下略)
この「蕪村三回忌追悼摺物」の紹介に続けて、次のように記している。
※『池田人物誌』に「桃田伊信」の条がある。すなわち氏は桃田、名は伊信。号は雪蕉堂・好古斎。明和二年三月廿日(「稲塚家日記」)池田で没した。蕪村が来池の時、適々この地へ来遊して邂逅したのではなく、宝暦……蜆子図の日初の賛に庚辰(宝暦十年)の年記がある……明和の頃には池田の荒木町(今の大和町で、一部には絵屋垣内といった所があった)に住み、池田に相当の画作をのこしている。たとえば呉服神社拝殿(宮司馬場磐根氏)
左右四枚の杉戸(各タテ一六九糎ヨコ一三八糎)の芦に鶴(向って右二枚)岩に大鷹(向って左二枚)の図とか、建石町法園寺観音堂天井の龍などはすぐれた大作であり。紙本半切の草画「蜆子図」(今所在不明)などもある。落款には「呉江法稿」とか「法眼伊信」などしるされているから、名実ともにすぐれた画家であったと思われる。その手法はすべて大和絵風を加味した狩野派であるが、その出生も画系も明白ではない。ただし『古画備考』の「御仏絵師」の条に神田宗信なるものがあって、その四代に伊信(明和二、正、廿六没、七十九)なる人があるが、この桃田伊信はそれに該当するのではないか。京都の人らしいがそれがどうして池田へ移ったかについては明らかにできない。もしかすると五代栄信に譲って隠棲したのかもしれない、伊信の墓は池田市桃園町の共同墓地にある。正面に「鋤雲翁法眼桃田伊信墓」、向って左側に「天保戊戌三月建之」また中段台石に「施主町中」とあって伊信没後七十三年に町内有志によって建碑されたことがわかる。
この記述によると、蕪村が十歳前後の頃に絵の手ほどきを受けたという絵師・桃田伊信は「京都の人らしい」が、池田在住の画家で、この池田には丹後時代以降の蕪村は何回となく訪れていて、その初期の頃に、この池田にてこの絵師・桃田伊信に再会したというのである。
(九十二)
※さて田福はその時点を「二十とせ余りの昔になりぬ」と記していることを拠点とすると天明五年(一七八五)から二十年前は明和二年(一七六五)となり、「余り」を考慮して宝暦末から明和初頭の頃となる。すなわち明和二年没した伊信の最晩年に当たり、蕪村は丹後遊学から帰って讃岐へ旅する前、五十歳の画俳両芸に名声愈々高まった頃池田へ来遊したことが明らかとなる。なお、田福が「伊信といへる書生に逢ひて四十とせふりし童遊を互に語り」といっている点に注目せねばならぬ。ここで「書生」とあるのは勿論いわゆる青年学徒といった意味でなく、画家とか学者を指したものと解する。また「童遊」は童同士の遊びということではない。伊信は明和二年には上掲の墓石の法眼から推して相当高齢と思われる。蕪村は五十歳で両人の年齢に大分の相違があるから、「四十とせふりし」によって、この童遊は享保九年頃、蕪村の八・九歳の童児の頃であり、伊信は三十余歳であったようである。つまり蕪村の童幼の頃に画家伊信と交わったことを意味する。このことは蕪村にとって重大な歴史の一こまといわねばならぬ。そこで思うのは、蕪村が伊信と画談し。或いは絵の手ほどきをうけたのではなかろうかということである。この頃は十歳になると絵けいこを始める風習があったから、この推定は無理ではない。少なくともこの伊信との童遊によって絵に関心を持ったということはいえるであろう。そうすると蕪村が生涯を画事に託した発端はこの頃にあったと私は思う。その場所はいずれか明らかにし難いが年齢から推して蕪村在郷の時とするべきであろう。これは憶測だが伊信が蕪村の毛馬の家に出入りしていたのではあるまいか。幼時における四十年前の思い出を、計らずも池田で再会し、留連追憶談笑したのであって、これは特筆すべき事実である。蕪村は天性絵が好きであった。それは追悼集『から檜葉』の「夜半翁終焉記」に「抑(そもそも)此(この)翁、無下にいはけなきより画を好(このみ)て」と几董がかいた記載と合致する。そして桃田伊信が蕪村幼童時の絵心に大きな刺激を与えたと考えられるのである。
岡田利兵衛氏は、「伊信が蕪村の毛馬の家に出入りしていたのではあるまいか」として、し、蕪村の生まれ故郷の毛馬村で、「蕪村の八・九歳の童児の頃」に、「伊信は三十余歳で」、「蕪村の童幼の頃に画家伊信と交わったことを意味する」というのである。しかし、蕪村はその毛馬村のことについては何一つ言い残してはいない。いや、その事実を隠し通そうという痕跡すらうかがえるのである。そして、蕪村の母は蕪村が十三歳の頃に他界している。岡田氏は上記のことを「憶測だが」としているが、「当時、蕪村は京都に居て、その京都で画家伊信と交わった」ということも、「憶測の域」は出ないが十分に考えられるところのものであろう。とにもかくにも、蕪村は十歳前後の頃に、専門絵師との交流があり、「無下にいはけなきより画を好(このみ)て」いたということは、その後の蕪村の生涯を考える上で貴重なことだけは、岡田氏が指摘するごとく、「これは特筆すべき」ことであろう。
(九十三)
岡田利兵衛氏は、その著『俳画の美』でこの桃田伊信と蕪村との出会いについて触れるとともに、『蕪村と俳画』所収の「蕪村の絵ごころ」でも同じようにこの出会いについて記述している。そして、その『蕪村と俳画』の「与謝蕪村小伝」ということで、次のような興味深い記述を続けている。
※蕪村の画の志向は、すでに十歳ならずして萌芽を見せていたのである。画精進の希望をいだきつつ一人旅ができるまで郷里にあって、やっと十七歳(享保十七年・一七三二)の頃、関東下向の本志をとげたのであった。江戸で俳諧は一応内田沾山についたといわれるが、元文二年(一七三七)夜半亭早野巴人が帰江したので、石町の夜半亭の内弟子として侍することになり、翌三年『夜半亭歳旦帖』に宰鳥の号で入集している。あらゆる修業において、蕪村が門下生として仕えたのはこの巴人だけで、画も書もすべて師匠をとらなかった。これは巴人が高潔の士であったからで、どんなにその道に長じても俗人であっては相手にしなかったのである。ところがその巴人が寛保二年(一七四二)に没したので、江戸の宗匠は俗人が揃っているので嫌気を催し、巴人門下の友人であった雁宕らの招きによって、留居十年の江戸を去って野総地方に赴くのである。画修業も江戸で積み重ねていたらしく、十四人の俳仙をかいた「俳仙群会図」がある。天明二年に人から頼まれて自ら書いた書詞が同貼されるが、それに「此俳仙群会図ハ元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして」と記されており、自ら元文の作であめことを証している。朝滄落款で大和絵風の手法、現存する蕪村画作の最古のものである。
この記述で、「やっと十七歳(享保十七年・一七三二)の頃、関東下向の本志をとげたのであった」ということについては、元文二年説(蕪村二十二歳)や享保二十年説(蕪村二十歳。この頃までに江戸に下るという説)と異なる。それは、上記の「俳仙群会図」(「此俳仙群会図ハ元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして」)の制作時期との関連で江戸下向を早めたということなのであろう。しかし、江戸に来て直ぐに、生存中の師の巴人をその俳仙の一人に入れているというのは不自然に思えることと、その印章の「丹青不知老至」が蕪村の丹後時代のものであることからして、蕪村が丹後宮津行きを決行した宝暦四年(一七五四)以降の作と考えると、蕪村十七歳の頃に江戸に下向したという必然性も乏しいように思われるのである。それよりも、巴人が京都に上洛した享保十三年(一七二八)以降の巴人京都滞在中に面識があり、その面識の後、享保十七年の頃、江戸に下向したということであれば、この享保十七年説も考えられないことではないという思いがするのである。
(九十四)
蕪村が十歳前後で、専門絵師の桃田伊信に絵の手ほどきを受けたということが事実としても、伊信は蕪村の絵画の師ということではなく、そもそも、蕪村は、画・俳二道の面において、蕪村自身師と仰いだ方は、当時、俳諧師として関東・関西一円に名を馳せていた夜半亭一世・早野巴人唯一人といって過言ではなかろう。そして、その絵画の面においては、画・俳二道の面において著名な英一蝶(画号・朝潮など)・小川破笠などの影響も受けていたのであろうが、なかでも、俳諧にも造詣が深く南画の画人・榊原(彭城)百川の影響は大きなものがあったろう。この百川の簡単なネット記事は次のとおりである。
http://www.sala.or.jp/~matu/matu5.htm
元禄十一年(一六九八)~宝暦三年(一七五三)。
画人。名古屋の人である。名は真淵。百川、蓮洲、八遷と称した。俳諧をよくした関係上、当初は俳画を得意とした。三十一才のとき、京に出て画業に専念した。博学であって、漢書を解したので、元明の図譜より南宗画(文人画)の画風を会得した。それがその後の彼の南画のもととなった。著作に「元明画人考」がある。高遊外との交遊もあった。江戸中期に活躍した画家の一人である。
興味深いことは、先に触れた蕪村の丹後宮津行きを決行したのが、この百川が亡くなる一年前の宝暦四年(一七五四)であり、何か百川の死と蕪村の丹後宮津行きとの関連もありそうな気配なのである。なお、この頃の蕪村の作品の「天橋立自画賛」には、次のような賛がしてある。
※八遷観百川は、丹青をこのむで明風(みんぷう)を慕ふ。嚢道人蕪村、画図をもてあそんで漢流(かんりゅう)に擬す。はた俳諧に遊むで、ともに蕉翁より糸ひきて、彼ハ蓮二(註・支考)に出て蓮二によらず、我は晋子(註・其角)にくみして晋子にならず。されや竿頭に一歩をすゝめて、落る処はまゝの川なるべし。又俳諧に名あらむことももとめざるも同じおもむきなり鳧(けり)。されど百川いにしころこの地にあそべる帰京の吟に、はしだてを先にふらせて行(ゆく)秋ぞ わが今の留別の句に、せきれいの尾やはしだてをあと荷物 かれは橋立を前駈(ぜんく)として、六里の松を揃へて平安の西にふりこみ、われははしだてを殿騎(でんき)として洛城の東にかへる。ともに此(この)道の酋長(註・風雅の頭領)にして、花やかなりし行過(註・道行)ならずや。
丁丑(註・宝暦七年)九月嚢道人蕪村書於閑雲洞中
(九十五)
蕪村の絵画の面でどういう影響を多く受けていたかということにおいて、桃田伊信・英一蝶・小川破立・彭城百川などを見てきたが、蕪村が「宰町自画」として初めて登場する元文三年(一七三八)に刊行された『俳諧卯月庭訓』の撰者の豊島露月との関係も特記しておく必要があろう。露月は蕪村の師の早野巴人と昵懇の俳諧師でもある。宗因系の露沾の門人で、沾徳、沾涼・露言などと同門で、巴人が元禄二年に京都から江戸に再帰して移り住む江戸本石町に居て、観世流謡の師匠をしながら、総俳書刊行の趣味をもち、多くのものを世に出している。この絵入り版本の一つの『卯月庭訓』に「宰町自画」として、その「鎌倉誂物」が収載されているというのは、元文三年、蕪村が二十三歳の頃、露月の目に留まるほどの絵画の面において実績を有していたということなのであろう。この「宰町自画」の「鎌倉誂物」は、挿絵としての版画であり、その彫師のくせなどもあり、当時の蕪村の画技を論ずることは危険な要素もあろうが、こういう刊行物の一端を担うということは、もうその頃までには、相当の技量を有していたということは言えるであろう。そして、それらのことは、蕪村の俳諧の面ので師の早野巴人はもちろん、その早野巴人を取り巻く夜半亭一門の俳人達は均しく認めるところのものであったのであろう。なお、露月のメモは下記のとおりである。
豊島露月〔本名、治左衛門、貞和。別号、識月・纎月・五重軒〕一七五一(宝暦一)・六・二没<享年八十五歳>・江戸本石町の俳諧師。露沾門下。観世流謡曲師。絵画の家元。撰集に『麻古の手』『江戸名物鹿子』『ひな鶴』『ふたご山』『ふたもとの花』『宮遷集』『倉の衆』など。句に<行年や手拍手にぬぐ腰袴>など。
(九十六)
蕪村は、後に大雅とともに、南画の大成者として日本画壇の中にその名を馳せることになるが、その先駆者としては、荻生徂徠門下で詩文をもってその名をうたわれた服部南郭と土佐の商家に生まれた中山高陽などが上げられる。そして。この南郭と若き日の蕪村に係わりについては、先に、「国文学解釈と鑑賞(昭和五三・三))所収の「蕪村・その人と芸術」(尾形仂・森本哲郎対談)の紹介記事で触れた。そして、この南郭・高陽に次いで、南画に大きな影響を及ぼした、祇園南海と柳沢淇園とについては、次のように紹介されている。
祇園南海
http://www.city.gojo.nara.jp/18/persons/nankai.html
延宝四(一六七六)年生、宝暦元(一七五一)年九月八日没。名は玩瑜、字は伯玉、通称は余一、号は南海、蓬莱、鉄冠道人、湘雲居など。和歌山藩医祇園順庵の長男。江戸で生まれ、元禄二(一六八九)年八月、新井白石・室鳩巣・雨森芳洲らが師事する木下順庵に入門する。父が没した翌元禄一〇(一六九七)年、その跡目を継ぎ、和歌山藩の儒者に二〇〇石の禄で任命され、和歌山に赴く。しかし、元禄一三(一七〇〇)年、不行跡を理由に禄を召し上げあられて城下を追放され、長原村(和歌山県那賀郡貴志川町)に謫居を命じられた。宝永七(一七一〇)年、藩主吉宗に赦されて城下に戻るまで習字の師匠として生計を立てた。正徳元(一七一一)年、二〇人扶持で儒者に復し、新井白石の推挙で朝鮮通信使の接待に公儀筆談を勤め、その功により翌二(一七一二)年、旧禄(二〇〇石)に復し、翌三(一七一三)年、藩校設立に際して主長に任命された。病死して和歌山の吹上妙法寺に葬られた。著作に『南海先生集』、『一夜百首』、『鍾情集』、『南海詩訣』、『南海詩法』、『詩学逢原』、『湘雲鑚語』などがある。
柳沢淇園
http://www.sala.or.jp/~matu/matu5.htm#柳沢淇園
宝永三年(一七〇六)~宝暦八年(一七五八)大和(奈良)群山藩の武人にして画家。曽根家の次男として生まれ、元服時藩主吉里より柳沢の姓と里一字を拝領し名を里恭とした。字は公美、号は淇園、竹渓、玉桂と称した。皆が柳里恭と呼んで慕った。多才多芸の人望家であったようだ。詩書画は勿論、篆刻、音曲、医療、敬仏の精神と万能な武士。いち早く南画を研究し文人画の先駆を成した。(畸人百人一首より)
この南画の先駆者の二人について、「江戸初期文人画 放蕩無頼の系譜」・[士大夫的性格の系譜](儒教的教養をもつ)と位置付け、さらに、「放蕩無頼を以て禄をうばう」「不行跡に付き知行召し放たる」(祇園南海)、「不行跡未熟之義、相重なり」(柳沢淇園)との記事が下記のアドレスで紹介されている。
http://www.linkclub.or.jp/~qingxia/cpaint/nihon24.html
これらのことと、蕪村没後二十三年たった文化三年(一八〇六年)に大阪で刊行され、当時の文学者の逸話を幾つか伝えている田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』の「夫(それ)蕪村は父祖の家産を破敗し、身を洒々落々の域に置いて」との蕪村にまつわる逸話とは、何か関連があるのであろうか。それとも、これらのことは単なる偶然のことなのであろうか。どうにも気がかりのことなのである。
(九十七)
この祇園南海と柳沢淇園の「不行跡」のことなどに関して、『南画と写生画』(吉沢忠他著)で、次のような興味のひかれる記述がある。
○南海と同様に淇園も「不行跡」が重なったという理由で処罰されている。これは単なる偶然の一致とは思われない。南海にしろ淇園にしろ、その学問の系統は朱子学であるが、道徳と密接にむすびついている朱子学に拘束されることはなかった。かれらには、詩文、芸術の世界がひらけていた。こうした文人的性格をもっていたがゆえに、絵画の世界に遊び「放蕩無頼」とか「不行跡」とみられたのか、あるいは、「放蕩無頼」「不行跡」とみられるような人物であったから、画を描くようになったのか・・・というより両者のあいだには相互関係があったのであろうが、とにかく日本南画の先駆者として数えられるひとびとが、おおやけにこうした烙印をおされていることは、注目してよかろう。淇園の学系は朱子学であったが、幼時から柳沢家の儒官荻生徂徠の影響を受けていた。そんなことからも朱子学に拘束されなかったのかもしれない。
蕪村が江戸に出てきた当時、服部南郭に師事したと思える書簡(几董宛て書簡)などに係わる対談記事について先に触れた。そして、この服部南郭は、京都の人で、元禄九年に江戸に出て、一時、柳沢吉保に仕え、後に、荻生徂徠門に入り、漢詩文のみならず絵画(画号は周雪など)にも造詣が深かったということなのである。蕪村の誕生した享保元年というのは、享保の改革で知られている徳川吉宗の時代で、この吉宗時代になると、綱吉時代に権勢を振るった柳沢吉保らは失脚することとなる。そして、その吉保の跡を継ぐ柳沢吉里は、綱吉の隠し子ともいわれている藩主で、その吉宗の幕藩体制の改革とこの柳沢由里と深い関係にある柳沢淇園の「不行跡」との関連、さらには、これまた、その吉宗によって失脚される新井白石とは同門(木下順庵門)である祇園南海の「不行跡」との関連など、何か因縁がありそうでそういう一連の当時の大きな幕藩体制の改革などもその背景にあるようにも思えてくるのである。そして、蕪村が師事したという、服部南郭もまた、淇園・南海と同じく、柳沢吉保並びに荻生徂徠門というのは、これまた何か因縁がありそうで、当時の蕪村の生い立ちや関心事のその背後の大きな要因の一つのように思えてくるのである。なお、服部南郭については、下記のアドレスで、次のように紹介されている。
http://www.tabiken.com/history/doc/O/O302L100.HTM
服部南郭
一六八三~一七五九(天和三~宝暦九)江戸時代中期の儒学者・詩人。詩文に長じ,学識豊かで世に容れられること大であった。通称小右衛門,名は元喬,字は子遷,南郭は号。京都の人。一六九〇年(元禄九)十四歳で江戸に出てきて十六歳で柳沢吉保に仕えた。壮年にして荻生徂徠の『古文辞説』に共鳴して門下となる。資性温稚で詩文の才能が世に知られ,北村季吟の門下であった父の感化もあって和歌も詠み絵画にも関心をもっていた。三十四歳のころ,家塾を開き門人を教授し古文辞の学を世に広めた。徂徠の門弟として,経学の太宰春台に対し詩文の南郭と並び称された。収入は年々百五十両あったと言われる。著書のうち四編四十巻にのぼる『南郭先生文集』は本領を発揮した詩文集。「大東世語」「遺契」にはその学識の広さが見られ,「唐詩選国字解書」「灯下書」「文筌小言」は詩文論として評判を高めた。南郭は政治・経済を弁ずることがない点に特徴があるとされている。
(九十八)
蕪村は、服部南郭に師事したというのが、それがどの程度のものであったのかは定かではない。南郭は、「政治・経済を弁ずることがない点に特徴がある」とされているが、朱子学の正統的な官学としての流れではない、在野の革新的な流れの荻生徂徠門であるということについては、やはり注目すべきことであろう。そして、従前の蕪村伝記については、これら荻生徂徠の影響ということについては等閑視してきたきらいがなくもない。そういうなかにあって、『蕪村 画俳二道』(瀬木慎一著)は「荻生徂徠の影響」という一項目をあげて、これらについて触れられていることは卓見というべきであろう。ここらへんのところを要約して紹介しながら、関連するようなことを記しておきたい。
○蕪村の学問・教養の基本を成したものがなんであったかについては、本人は明らかにしていない。しかし、かれが大阪の近郊の半農・半工的環境で成長した享保期の学問的状況は判明しているし、また、画俳として身を立ててからの知識の源泉は、その作品から相当程度掘り当てられる。一口に言うならば、それは朱子学のなかの構造論的な系列である。と言えば、直ぐさま念頭に浮かぶのは、荻生徂徠である。徂徠の学問は多岐にわたっているが、その最大の特徴は、政治の世界を道徳とは別のものであると見たこと、そして、文芸・思想においては言語の機能を重視したことに要約できるだろう。それは、道徳的規範を以てすべてを律しようとした従前の文教政策に対する最大の異論であった。
※上記は瀬木前掲書の出だしの部分なのであるが、それに、次のようなことが付記できるのではなかろうか。「蕪村が、その生涯を通して追求して止まなかった、『南画と俳諧』というのは、当時の社会の根底に流れていた、いわゆる朱子学の道徳的規範遵守とは相容れない世界のものであった。ここで、蕪村は荻生徂徠の世界に多くの点で共鳴し、その徂徠門にあって、己が生涯を賭けようとしている『南画と俳諧』の面での先駆者たち(祇園南海・柳沢淇園・彭城百川等)とその先駆者たちと同じ反俗・反権威の清高な気品を保ち続けた俳諧師・早野巴人をその生涯の師とし、それらの師の教示を生涯にわたって実践し続け、その『画俳二道』の頂点を極めた、その人こそ、蕪村であった」と、そんな感慨を抱くのである。
なお、荻生徂徠のネット紹介記事は以下のとおりである。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~MARUYAMA/tokugawa/sorai.htm
荻生徂徠
綱吉に仕える医師方庵の二男として江戸二番町に生まれる。名は双松、字は茂卿のち茂卿、通称は惣右衛門。はじめ朱子学を学ぶ。伊藤仁斎の古義学を攻撃したが、のち『弁道』『弁名』を著わして、さらにより徹底した古文辞学の立場を確立。1696年(元禄9)以来柳沢吉保に仕え、政治顧問的役割を果たす。 吉保に赤穂浪士の意見を求められ、『擬自律書』を著して処分を上申した。徳川吉宗の内命によって『太平策』『政談』を著し、時弊救済策を述べた。門人に経済理論の太宰春台、詩文の服部南郭らをを輩出し、またその文献学的方法態度は、国学に影響を与えた。元禄・享保時代の社会的変動を思想面に於て最も痛切に受容して、その時代的社会的な問題性と真正面から取り組まんとしたのは、徂徠学である。それはまさしく時代の子であった。さればこそ、成立と共にたちまちにして思想界を風靡し、他派を圧倒するの勢を示したのである。また同時に、時代の子たるが故に、この時代の含む矛盾を自らの中に刻印しており、やがては没落すべき運命をも有していたといえよう。徂徠がその名声を獲得したのは、未だ朱子学者としての立場から古文辞学を打ち樹てたときのことであるが、徂徠学としてのオリジナリティを確立したのは、享保二年の『弁道』及び『弁名』の二書を以てであった。(中略)徂徠学は、一面彼のパ-ソナリティと密接に結びついており、彼のパ-ソナリティは元禄精神の象徴であったとも考えられる。とりわけ、その不羈奔放な豪快さが見られることである。彼は、「熊沢(蕃山)の知、伊藤(仁斎)の行、之に加ふるに我の学を以てせば、則ち東海始めて一聖人を出さん」(先哲叢談)と自負した。故に権門に服するを潔しとせぬ初期からの気風が見られる。徂徠学はなによりもまず政治学たることを本質とする。一面からいえばそれは、徂徠学が修身斉家治国平天下を標語とする儒教思想に属することの当然の結果とも見られるが、他の一切の儒教に於ては政治的なるものは最後的な帰結として現われ、出発点となるのは個人道徳であるに反し、徂徠学では逆に「出発点」をなす。すなわち、政治的価値は常に先行者の地位を占め、個人ないし家族の倫理的な義務の履行という回路を経ないで、端的にその実現が求められた。 彼は問題を二つに分けた。一は、機構の面、他は、これを具体的に運営している人間の面である。そして彼は、この両面から社会病理を追求した。前者について指摘した矛盾は、何よりも第一に、彼が「旅宿の境界」と呼ぶところの武士生活の矛盾であった。(中略)第一には、「旅宿ノ境界」からの武士の脱却をはかること - そのために、武士は領地に帰り、土着して大規模に再生産に従事すること、また戸籍を作成し「旅引」(旅行証明書)を発行して人々の移動を統制することである。第二は、「礼法」を確立して、身分制度を樹立すること。このことは「礼楽」に「道」を求めた徂徠の基本哲学の具体化であり、徂徠学の本来的な思惟方法の発現であって、しばしば誤解されるような「法家」的立場の現われでは決してない。徂徠によれば、朱子学がかかる観念的思弁に陥った論理的要因は、「大極」を「理」としてこれに究極的価値をおくところの儒教的自然法思想に胚胎する。理がいかなる時代にも、またいかなる社会制度にも常にその根底に在って無時間的に妥当しているという考え方、そかもその理は決して現実の社会規範ないし制度を超越せるものではなく、それと必然的な牽連関係を以て、そのような規範に内在するものである以上、かかる理の優位の破壊なくしては、制度的変革を論理的に基礎づけることはできない。つまり「制度ノ立替」と彼がいう場合、その担い手となるのは従来の制度のなかにある人格ではなく、むしろ従来の制度ないし規範から超越した人格である。つまり制度の客体でなくて、それに対し、主体性を有するような人格の予想の下に始めて可能なのである。換言すれば、理の優位でなく、いかなるイデ-をも前提しない現実的具体的な人格を基礎におくことにより、始めて無時間的な理の妥当性が破られうるのである。
(『日本政治思想史講義録』1948 169-180頁 第七章 儒教思想の革命的転回=徂徠学の形成)
(九十九)
『蕪村 画俳二道』(瀬木慎一著)の「荻生徂徠の影響」は次のように続ける。
○徂徠の学問的立場は、通常「古文辞学」と呼ばれれているように、明の文学における「古文辞」に先例を求めたものであるが、それが単なる復古運動にとどまるものでなかったことは吉川幸次郎の説明によって了解される。
「……精神のもっとも直接的な反映は、言語であるとする思想である。したがって精神の理解は、言語と密着してなすことによってのみ、果たされるとする思想である。」
そこで古典を読むばかりでなく、自分も古典の言葉で書き、考え、そしてその精神を把握することをめざしたわけである。その結果明らかになることは、儒者共の説く人為的な道徳律の虚妄さであり、それを排除するとき「理は定準なきなり」という世界観に到達する。つまり、世界は多様性において成り立っているのであり、そこに生きる人間の個々の機能を尊重するという考え方である。「人はみな聖人たるべし」という宋学の命題とは正反対に、徂徠は、「聖人は学びて至るべからず」という方向を提示し、人が個性に生き、学問によって、自己の気質を充実させ、個性を涵養しうる可能性を強調している。
※この徂徠の蕪村への影響は、蕪村をして、当時の絵画の主流であった中国北宗画を基本する狩野派よりも、蕪村が生をうけた享保時代前後に入ってきた反官的立場の南宗画に目を向けさせ、蕪村より八歳年下の大雅とともに、その中国風を払拭して日本独特の南画を樹立していくこととなる。そして、そのことは同時に、当時の御用絵師の狩野派の画人からは「文人趣味の手すさび」と批判され、特に蕪村は、中国的規範を遵守する正統的な南画派の画人からはその俳諧的興趣により「橘にして正ならず」(田野村竹田)との「邪道」ともとれる批判をも甘受することとなる。そして、『蕪村 画俳二道』(瀬木慎一著)の「漂泊の蕪村」において、次のように「蕪村の蕪村たる所以」を記述している。
○蕪村の蕪村たるゆえんは、画俳であることである。俳人であり、画家であり、また、俳人でもなく、画家でもなく、字義どおり「画俳」という以外にはない蕪村。かれをめぐる論議は止むことなく、いつまでも続くとしても、唯一つ明らかなことは、この復元的にして融合的な不定型の個性を測る尺度は、「近代」にはないということである。
※この蕪村の「画俳」二道の「復元的にして融合的な不定型の個性」は、まさしく荻生徂徠とその学派による影響によるものであろうし、そして、この蕪村をして、その個性を測る尺度は、「近代」にはないというよりも、「現代」においてもないといえるのではなかろうか。そして、つくづく思うことは、「近代」・「現代」とを問わず、「画俳」二道の面において、蕪村と同じレベルに達しているという「復元的にして融合的な不定型の個性」を見出すことは不可能なのではなかろうか。これらのことに思いを巡らすときに、蕪村が突如として、西洋の近代詩に匹敵するような古今に稀なスタイルと内容の俳詩「北寿老仙をいたむ」(「晋我追悼曲」)やその絵画化とも思われる「夜色楼台雪万家図」などをこの世に残しているその必然性をも垣間見る思いがするのである。
(一〇〇)
蕪村はその存命中は俳諧師というよりは画人として名が馳せていた。安永四年(一七七五)・天明二年(一七八二)の『平安人物志』にも、いずれも画家の部にあげられている。
安永四年
http://isjhp1.nichibun.ac.jp/contents/Heian/00065/fr.html
天明二年
http://isjhp1.nichibun.ac.jp/contents/Heian/00110/fr.html
蕪村は、俳諧師として、明和七年(一七七〇)に夜半亭一世宋阿こと早野巴人の跡を継ぎ夜半亭二世となるが、いわゆる、俳諧師としてその生計をまかなうのではなく、あくまでも画人として暮らしを立て、点者(宗匠)として金銭を貪る当時の俳諧宗匠に対して批判的であった。その俳句も絵画的であることが大きな特徴であることは言をまたない。そして、その俳論も、実は当時の中国画論の影響が著しいのである。蕪村の俳論の代表的なものとして、安永六年(一七七七)『春泥句集序』に書かれた「離俗論」がある。
○画家ニ去俗論あリ。曰、画去俗無他法(画ノ俗ヲ去ルニ他ノ法無シ)、多読書則書巻之気上升(多ク書ヲ読メバ則チ書巻ノ気上升シ)、市俗之気下降矣(市俗ノ気下降ス)、学者其旃哉(学者其レ旃(こ)レ慎マンカナ)。それ画の俗を去(る)だも筆を投じて書を読(よま)しむ。況(や)詩と俳諧と何の道遠しとする事あらんや。
『南画と写生画』所収の「南画の大成……池大雅 与謝蕪村」(吉沢忠稿)で、これらのことに関して次のように記している。
○画に俗気をなくすには、多くの書を読まなければならないとするこの去俗論は『芥子園画伝(かいしえんがでん)』の「去俗」からそのまま引用したものであるが、それを蕪村は俳諧に応用したのである。ここに、蕪村の画俳一致論はその理論的根拠をみいだしたのである。
そして、この蕪村の画俳一致論は、南画の先駆者の一人である柳沢淇園の、「先(まず)、絵もから絵(唐絵)より学ぶべし。絵をかく人の常に見るべきは芥子園伝也」(『ひとりね』)の影響下にあることは、これまた言をまたないであろう。ことほど左様に、蕪村は、荻生徂徠とその系譜者たちの影響を、その生涯にわたって享受し、そして、それを忠実に実践していったのである。
若き日の蕪村(その九)

若き日の蕪村(その九)
(一〇一)
『南画と写生画』(吉沢忠著・小学館)では、蕪村の「春風馬堤曲」に関連させ、次のとおり独特の蕪村の絵画論を展開している。
○「春風馬堤曲」は、蕪村の故郷毛馬から大阪に出た女が、帰郷して、毛馬の堤にさしかかったときの有様を、漢詩、自由詩、俳句をおりまぜながらうたった、きわめて異色のある詩である。ある意味では、この三種の文体が蕪村の絵画、ことに晩年の謝寅時代の絵画にあらわれている、といえなくもなさそうである。つまり漢詩は、南宗的なものを基調としながら、北宗的なもをまでまじえた蕪村の中国画系統の画、文語体の自由詩は、格調高く迫力にとむ独特の水墨画、そして俳句に対応するものは、俳画を主とした和画系統の画である。
この漢詩的なスタイルに匹敵する「中国的系統の画」(南画)、自由詩のスタイルに匹敵する「水墨画」(南画と俳画との一体化)、そして、俳句のスタイルに匹敵する「和画系統の画」(「俳画」・「俳諧ものの草画」)の、この三つの蕪村の絵画の区分けは、蕪村の絵画の鑑賞上、大きな示唆を与えてくれる。いや、画俳二道を極めた蕪村の生涯を辿る上での必須のキィワードといっても過言ではなかろう。蕪村が始めて登場するのは、豊島露月が編んだ絵入り俳書、『俳諧卯月庭訓』の「鎌倉誂物」(宰町自画)であった。これは、上記の分類ですると、「和画系統の画」に該当し、それは、二十代前半の江戸時代の蕪村を象徴するものでもあろう。そして、その江戸を後にし、京都に再帰して、丹後に絵の修行に出かけた後、讃岐に赴く。ここで、「階前闘奇 酔春星写」と記した「蘇鉄図襖絵」(現在は屏風に改装)を描く。これは、上記の分類の「水墨画」であり、中国風でもなく、されど、俳画風でもなく、その後の画人・蕪村を暗示するような、丹後・讃岐時代の四十代・五十代前半の蕪村を象徴するようなものであろう。しかし、蕪村のその六十八年の生涯において、上記の分類ですると「中国的系統の画」(南画)が最も多く、それは、当時の時代的な一つの風潮であった、祇園南海・柳沢淇園・彭城百川らの、いわゆる勃興期にあった日本南画の影響を最も多く享受した結果ともいえるであろう。そういう意味で、蕪村は大雅とともに「日本南画の大成者」との名を冠せられるのは至極当然のことではあろう。しかし、上記の分類はあくまでも便法であって、とくに、最晩年の、安永七年(一七七八)以降の落款「謝寅」時代の絵画は、上記の分類を超越して、いわゆる「謝寅時代の絵画」として、上記の分類によることなく、独自に鑑賞されるべきものであろう。そして、この時代のものは、「夜色楼台雪万家図」・「峨嵋露頂図巻」・「春光晴雨図」・「奥の細道屏風」など傑作画が目白押しなのである。まさに、蕪村は晩成の画人であり、俳人であり、そういう意味では、常に研鑽を怠らなかった努力の人であったということを、つくづくと実感する。
(一〇二)
『南画と写生画』(吉沢忠著・小学館)では、蕪村の「春風馬堤曲」に関連させての、「中国画系統の画、水墨画、俳画を主とした和画系統の画」の三区分のうちの「俳画」(俳諧ものの草画)について見ていきたい。
安永六年(一七七九)と推定される蕪村の几董宛ての書簡に、「はいかい物の草画、凡(およそ)海内に並ふ者覚無之候」との一文があり、蕪村は、この「俳画」(俳諧ものの草画)ということにおいて、相当の自信と相当の覚悟を持っていたことが伺えるのである。その俳画の頂点を極めたものが、芭蕉の紀行文『おくのほそ道』に関連するもので、現在、画巻が三巻、屏風一隻、模写一巻が残されており、それらを年代順に列挙すると下記のとおりである。
一 画巻 右応北風来屯需自書干時安永戌戊(七年)夏六月 夜半亭蕪村
二 画巻 安永戌戊(七年)冬十一月写於平安城南夜半亭自書 六十三翁蕪村
三 屏風 安永己亥(八年)秋平安夜半亭蕪村写
四 画巻 右奥細道上下二巻応維駒之需写於洛下夜半亭閑窓干時
安永己玄(八年)冬十月 六十四翁蕪村
五 画巻(模写) 安永丁酉(六年)八月応佐々木季遊之需書
於平安城南夜半亭中 六十二翁蕪村
この二番目の図巻は、現在、逸翁美術館蔵のもので、上下二巻の十四面(旅立ち・那須の小姫・須賀川軒の栗・佐藤嗣信らの嫁・塩釜の宿・高館・尿前の関・山刀伐峠・長山重行亭・市振の宿・曽良先行惜別・大聖寺の全昌寺・等栽草庵・大垣近藤如行亭)で構成されている。そして、三番目の屏風が、山形県立美術館蔵のもので、重要文化財に指定されている。この構成は、その六曲に『おくのほそ道』全文を草し、逸翁美術館蔵の図鑑と同じようなスタイルで、九面(旅立ち・那須の小姫・須賀川軒の栗・佐藤嗣信らの嫁・塩釜の宿・尿前の関・長山重行亭・市振の宿・大垣近藤如行亭)が配置され、全体でまるで一つの画を見るように工夫されている。こういうものは、まさに、画・俳二道を極めて、俳聖・芭蕉の『おくのほさ道』を知り尽くした蕪村ならではの傑作俳画の極地と言えるであろう。そして、蕪村はそのスタートにおいて、露月撰の『卯月庭訓』の「宰町自画」とある「鎌倉誂物」の挿絵(版画)に見られる如く、これらのものを自家薬籠中のものにしていた
ということについては、先に見てきたところのものである。そして、これらの蕪村の生涯の業績は、まさに、「はいかい物の草画、凡(およそ)海内に並ふ者覚無之候」という趣を深くするのである。
(一〇三)
先に触れた、柿衛文庫所蔵の「俳仙群会図」(画像・下記アドレス)については、内容的には、古今の俳人から、宗鑑・守武・長頭丸(貞徳)・貞室・梅翁(宗因)・任口上人・芭蕉・其角・嵐雪・支考・鬼貫・八千代・園女・宋阿の十四人の俳人を肖像画的に描き、さらに十三人の代表句も記されており(その画作とは別な時点ではあるが)、俳画の範疇に入るのだろうが、そのスタイルは当時の人物画・肖像画に見られる典型的な筆法(狩野派と土佐派の折衷様式)で、蕪村自身が言っている「俳諧ものの草画」(俳画)とは異質なものであろう。そして、この「俳仙群会図」については、その画賛の「此俳仙群会の図は、元文のむかし、余弱冠の時写したるものにして、ここに四十有余年に及べり。されば其稚拙今更恥べし。なんぞ烏有とならずや」との元文年間に制作されたものではなく、「『朝滄』の落款から推して、四十代初頭の丹後時代の作」(『蕪村全集四』)ということについては、先に触れたところである。
http://hccweb6.bai.ne.jp/kakimori_bunko/shozo-buson.html
この「俳諧ものの草画」(俳画)は、一般的には略画・草筆・減筆などともいわれ、簡略な単純化された表現スタイルをとり、この単純化されたスタイルが、丁度、五・七・五と最小の短詩型表現スタイルの俳句と相通ずるものを有している。そして、この略画・草画はしばしば版本となって、この版本が「翻刻・模刻・改刻」などがなされ、いわゆる、蕪村画の「三十六俳仙図」などは、河東碧梧桐によると、「蕪村『俳諧三十六歌仙』は偽作なり」と完全な否定論までなされるに至っている。しかし、まぎれもなく、蕪村はこれらの「俳諧ものの草画」(俳画)では、そのスタートの時点からその晩年の先に触れた「おくのほそ道」関連の図巻などに至るまで、この面においては傑出した画・俳人であり、この流れが、蕪村門下の月渓・九老・金谷などに引き継がれているのである。さらに、蕪村自身、その源流を探ると、英一蝶・野々口立圃・僧古澗明誉・彭城百川などの影響などを受けており、また、渡辺崋山などの別系統のものもあり、この「俳諧ものの草画」(俳画)という世界も、江戸時代を代表する浮世絵と同じく、一つのジャンルを形成していたということも特記しておく必要があろう。そして、この「俳諧ものの草画」(俳画)において、蕪村は自他共に認める第一人者であったことは言をまたない。
(一〇四)
蕪村の画業の一つとして、この世にその名をとどめている露月撰『俳諧卯月庭訓』の「鎌倉誂物」も版本の挿絵といってもよいものであろう。この蕪村の挿絵は蕪村俳画の源流といえるもので、この挿絵的な俳画が制作された元文二年(一七三七)当時の、蕪村の肉筆画というものは存在しない。そして、その肉筆画が蕪村作としてその名をとどめているものは、その多くが結城・下館のものであって、その作品は以下のとおりである。
○ 陶淵明山水図 三幅対 子漢 下館・中村家
○ 三浦大助・若松鶴・波鶴図 三幅対 四明 同上
○ 漁夫図 一幅 浪花四明 同上
○ 追羽子図 杉戸絵四面 なし 同上
○ 文微明八勝図 紙本淡彩一巻 伝蕪村模 同上
○ 高砂図 三幅対 浪華長堤四明・四明 下館・山中家
○ 人物図 三幅対 浪華長堤四明・四明 下館・板谷家
○ 墨梅図 紙本墨画四枚 なし 結城・弘経寺
○ 楼閣山水図 紙本墨画六枚 なし 同上
これらの作品が描かれた年代は定かではないが、蕪村の師の早野巴人が亡くなった寛保二年(一七四二)から京に再帰する宝暦元年(一七五一)の約十年間のものであることは確かなところであろう。その落款の「子漢・四明・浪花四明・浪華長堤四明」などからして、これらの作品以外にも相当数の作品を描いたであろうことも容易に想像されるところではある。そして、上記の結城・下館時代の作品のうち、蕪村模写とされている「文微明八勝図」などは、蕪村が本格的に南画を学ぶ切っ掛けになったものであろうと推測されており、この結城・下館時代が、それまでの方向性のなかった蕪村絵画が南画的な方向に舵取りをされた頃であろうといわれている。これらについて、『蕪村 画俳二道』(瀬木慎一著)では次のように記されている。
○『八種画譜』とは中国の八種の画譜を集めたもので、明末の天啓年間にまとめられて板行され、まもなく、日本にもたらされた。寛文十一年に日本でも困難を克服してようやく翻刻され、さらに宝永七年に再刻された。同じく元禄年間に翻刻された『芥子園画伝』と共に、南画を学ぶものにとっては、それは必要不可欠の教本であった。『芥子園画伝』とは異なり、純粋に南宗的ではないが、それまでよく知られていなかった明画の様式を伝えて、文人墨客に利用され、日本における南画の興隆を促した。関東時代の蕪村は、寛延元年に翻刻されたばかりの『芥子園画伝』の方はまだ見る機会がなかったのではないかと考えられるだけに、『八種画譜』は熱烈に学び、模写をしたことが充分に考えられる。
(一〇五)
「若き日の蕪村」というのは、年代的には、蕪村が京に再帰する宝暦元年(一七五一)以前の、蕪村、三十六歳以前のこととして概略的に使用している。そして、この「若き日の蕪村」時代の初期の絵画の遺品も、また、俳諧(連句・俳句)関連の作品も共に極めて少なく、蕪村がその画俳の二道において真にその名を世に問うて来るのは、京に再帰して、宝暦四年(一七五四)に丹後の宮津行きを決行する以後ということになろう。すなわち、年齢的には、蕪村、四十歳以後ということになる。この四十歳から亡くなる天明三年(一七八三)、六十八歳までの、後半の蕪村の生涯というのは、前半の蕪村の生涯と比して、その情報量も著しく多く、その足跡を辿るということも容易ではあるけれども、いかんせん、その前半の生涯を辿るということは、凡そ至難なことといっても過言ではなかろう。しかし、その前半生の少ない情報を垣間見るだけでも、巷間公然と言われているようなことについて、「果たしてそれは真実なのであろうか」と、そういう洗い直しが必要なのではなかろうかという思いを深くするのである。そのうちの一つとして、蕪村没後二十三年たった文化三年(一八〇六年)に大阪で刊行され、当時の文学者の逸話を幾つか伝えている田宮橘庵(仲宣)の『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』の「夫(それ)蕪村は父祖の家産を破敗し、身を洒々落々の域に置いて」との逸話についても、単に、「洒々落々の『南画』や『俳諧』に身を置いて」のような意味合いで、南画の先駆者たちの、「放蕩無頼を以て禄をうばう」「不行跡に付き知行召し放たる」(祇園南海)、「不行跡未熟之義、相重なり」(柳沢淇園)と同じようなことなのではなかろうかと・・・、そんな思いもしてくるのである。また、蕪村は己の出生について、「何も語らず、むしろ、それは隠し続けた」ということなどについても、先に触れてきたところであるが、上記の結城・下館時代の絵画作品の落款の「子漢・四明・浪花四明・浪華長堤四明」などを改めて見直すと、蕪村は、「摂津の毛馬の馬堤の遠くに比叡の四明峰を仰ぎ見る」所て生まれ、育ったということをはっきりと語りかけているようにも思えてくるのである。(この時点で、一旦、この「若き日の蕪村」の点と線を結ぶ作業を一区切りとして、「回想の蕪村」ということで、また、違った視点での点と線を結ぶ作業に移ることとしたい。)2006/08/02 一応了。